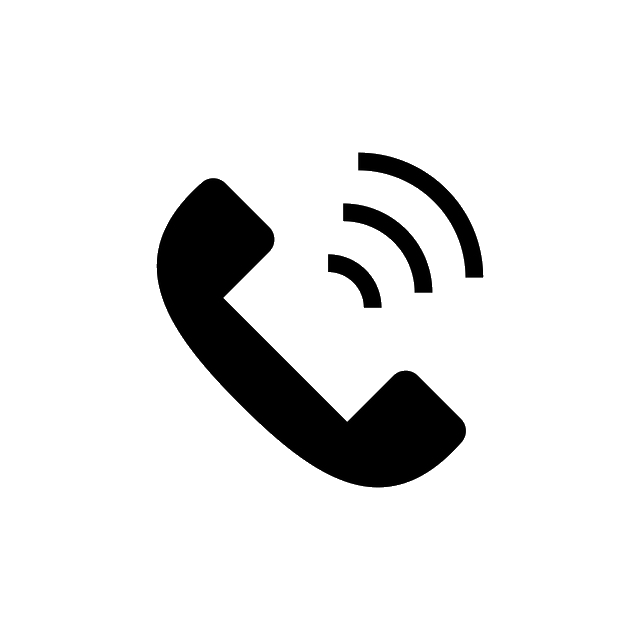上陸の許可について
この記事では、入国と上陸の違い、上陸の許可条件について解説しています。入管法の基礎知識として知っておくとよいと思います。
1.入国と上陸の違い
「入国」とは、簡単に言えば「日本の領海か領空に入ること」です。ですので、客船や国際線の飛行機の乗客は、日本の領海(空)に入った時点で「入国した」ことになります。空港、海港に着いた時点では、日本の領海(空)に既に入っている状態です。つまり、事前に(自国を出国する前に)日本に入国する許可がなければ不法入国ということになってしまいますよね? では何をもって入国が事前に認められているのかというと、旅券(パスポート)と査証(ビザ)になります。
空港、海港に到着して上陸審査を受ける段階では、一応、陸の上には居るのですが「上陸」とはなりません。上陸審査を通って始めて上陸となります。
2.査証(ビザ)の役割
査証(ビザ)は、上陸、滞在許可を保証するものではなく、上陸許可のための条件の一つにすぎません。上陸審査の結果、上陸拒否事由に当たることが発覚したような場合は、上陸は許可されないことになります。
査証(ビザ)は、上陸審査を受けた時点で使用済みとされ、外国人が日本に上陸し、日本に滞在できる根拠は「上陸許可」になります。
※ ただし、数次ビザは、有効期間満了まで使用済みとはなりません。
補足ですが、空港、海港の入国審査では、普通は上陸審査とは言わずに入国審査と言っているかと思いますが、実際に行われるのは上陸審査です。
3.上陸できるための条件
それでは、上陸できるための条件は、どのようなものでしょうか。上陸のための条件は以下のとおりです。
<上陸のための条件>
① 有効な旅券(パスポート)及び日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していること
② 申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
③ 我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること
また、上陸許可基準のある在留資格については,その基準に適合すること
④ 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
⑤ 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと
以下に、詳しく解説していきます。
① 有効な旅券(パスポート)及び日本国領事官等が発給した有効な査証(ビザ)を所持していること
旅券(パスポート)が偽造されたものでないかどうか、期限が切れていないか、及び査証(ビザ)があるか、有効であるかが審査されます。旅券(パスポート)は、国籍保有国の政府が所持者の「渡航を認め」、「国籍を有することを証明」し、渡航先の国家に対して「人身保護を要請する」書類です。旅券(パスポート)には身分事項として所持者の国籍・氏名・生年月日・性別が記載され、このほかに旅券番号・発行年月日・有効期限・発行機関なども記されています。
査証(ビザ)「上陸許可」の証印には、日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」、日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示されます。
有効な査証(ビザ)の所持は、空港、海港において、入国審査において、上陸申請を行うための要件です。
② 申請に係る活動(我が国で行おうとする活動)が偽りのものでないこと
「活動の非虚偽性」といいますが、日本で行おうとする活動が社会通念に照らして「虚偽のものではない」ことを立証する必要があります。
③ 我が国で行おうとする活動が,入管法に定める在留資格のいずれかに該当することまた、上陸許可基準のある在留資格については,その基準に適合すること
「在留資格該当性」、「上陸許可基準適合性」といいますが、「在留資格該当性」については、就労系、身分系のいずれの在留資格においても、日本で行おうとする活動が、在留資格に該当する必要があります。ただし、「永住者」、「高度専門職2号」は、当該資格での上陸を想定しておらず、他の在留資格からの資格変更によるものであるため当該資格での上陸はできません。
また「定住者」については定住者告示に定める類型に当たる者に限られます。
「上陸許可基準適合性」については、「高度専門職1号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」,、「興行」、「技能」、「技能実習」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「介護」、「特定技能1号、2号」(平成31年4月から)に適用があります。
入管法は、在留資格該当性とは別に、上陸許可についてのみ、在留資格に係る要件として、上陸許可基準を定めています。
※上陸許可基準は、資格毎に定められていますので、その内容については、資格別の記事を参照ください。
※「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「文化活動」、「短期滞在」には上陸許可基準はありません。
上記の②、③の各条件については、それを満たすことを、あらかじめ法務大臣に認定を求めることができます。それが「在留資格認定証明書」交付申請です。
「短期滞在」を除いて、「在留資格認定証明書」を取得していれば、在外公館での査証発給も容易になり、また空港、海港での上陸審査においても、上陸のための②、③の各条件を満たすことの立証が容易になります。
外国人が空港、海港に到着して上陸審査の場において、短時間で上記の上陸のための条件のすべてについて立証することは困難ですので、法務大臣の事前認定制度を設けることで、入国審査手続きの簡易化と迅速化を図ることを目的にしているものです。
④ 滞在予定期間が,在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること
外国人の滞在予定期間が、入管法施行規則別表第2に掲げられている最も長期の在留期間超えないこと。
⑤ 入管法第5条に定める上陸拒否事由に該当しないこと
入管法第5条の条文で定める事由のいずれかに該当する外国人の上陸は原則として拒否されます。国家は,その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり、各国とも公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。
日本では、上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で、具体的には次のような類型の外国人について日本への入国を拒否するとされています。
① 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③ 日本から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④ 日本の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者
4.上陸拒否事由
ここでは、上陸拒否事由のそれぞれの具体的な内容について解説します。
上陸を許否する根拠は、「入管法第5条」によります。
国家は,その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり、各国とも公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。
外国人が日本に入国する自由は保障されていません。
日本では、上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で、具体的には次のような類型の外国人について日本への入国を拒否するとされています。
① 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
② 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
③ 日本から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
④ 日本の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
⑤ 相互主義に基づき上陸を認めない者
参考記事
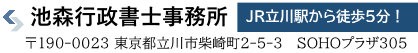


.jpg)