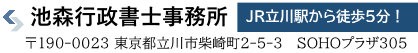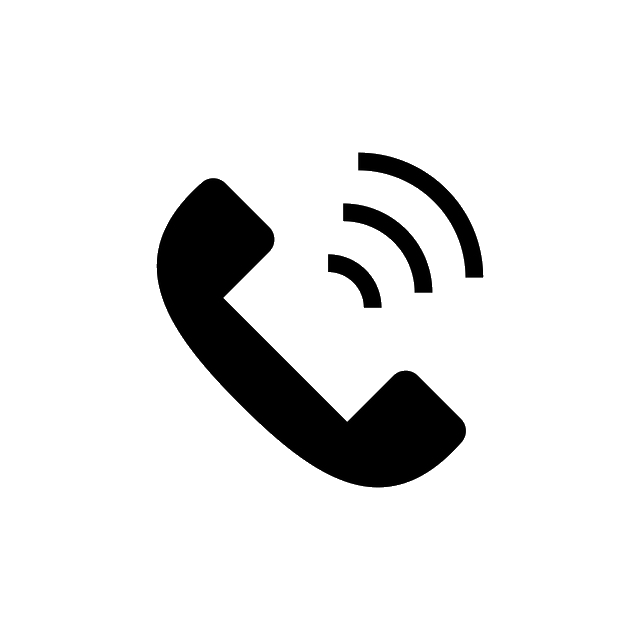アポスティーユ・文書の認証について
「アポスティーユ」は、日本の官公署,自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じた場合、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合や日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。「公印確認」も同様の外務省の証明のことです。
「アポスティーユ」は、公印確認と異なり、公文書に直接押印せずに「付箋」が付与されます。これにより駐日領事による認証がなくとも、駐日領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することが可能となるのです。アポスティーユによって、海外では日本から発行された真正な書類として扱われます。
アポスティーユ(apostille)
「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。提出先国はハーグ条約締約国のみです。アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館に確認を忘れないようにしましょう。ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。
公印確認
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得します。
私文書はそのままではアポスティーユを受けることはできませんが、公証役場で公証人認証を受ければ公文書としてアポスティーユを受けることができます。そのため私文書はまず公証役場で公証人認証を受けましょう。
公証人認証とは、私文書に対して、その私文書に記載されている作成者の署名や記名押印が真正なもので、本人によって作成されたものであるということを、公証役場で公証人が証明することをいいます。
公証人認証を受けた文書は、公証人が所属する地方法務局長による公証人押印証明が必要です。
このように公証人によって認証され、法務局長による公証人押印証明を受けた文書は、公文書として取り扱われ、外務省でアポスティーユを受けることができます。
ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約加盟国と非加盟国の各々について、日本で作成した文書の提出方法が違いますので、それらを説明します。
公文書と私文書
まず、日本の役所が発行した「公文書」と私文書では外国の役所に提出する手続きが異なります。
日本の公文書としては、戸籍謄本、住民票、婚姻要件具備証明書などがあります。
婚姻要件具備証明書は、外国で先に婚姻手続きを行う場合に、日本の役所で取得して外国の役所に提出が求められます。
婚姻要件具備証明書の取得方法は、日本の法務局で取得する方法と、外国の日本大使館・領事館で取得する方法とがあります。(国によっては、法務局のものでないと受付けてくれないので、法務局の方をお勧めします。)
私文書ですが、これらの日本語の公文書を、翻訳会社に依頼するか、または自分で外国語に翻訳した翻訳文書は、公文書ではなく私文書に当たります。
国際結婚の手続きにおいて、外国で先に婚姻手続きを行う場合には、日本人配偶者の婚姻要件具備証明書などの文書と、外国語翻訳文書の提出が求められますが、これらの文書は、提出先がハーグ条約加盟国の場合は、アポスティーユ(APOSTILLE)という公印証明が、非加盟国の場合は、その国の在日大使館・領事館での認証が必要になります。
日本での文書認証手続きの流れ
婚姻要件具備証明書は市区町村役場でも取得できますが、ここでは法務局で取得する方法で記載しています。
(国によっては、法務局のものでないと受付けてくれないので、法務局の方をお勧めします。)
| ハーグ条約 | 公証役場の管轄 | 手続きの流れ |
|---|---|---|
| 提出先が加盟国の場合 |
東京都、神奈川県、 |
(公証役場の「ワンストップサービス」あり)
以上で、日本の手続きは完了です。法務局と公証役場に行くだけです。 |
| 上記以外 |
(公証役場の「ワンストップサービス」なし)
アポスティーユの必要書類 証明が必要な公文書は、以下に注意してください。 【必要書類】 下記のような場合には、代理申請であっても委任状を省略することができます。 ・返送用封筒(郵送による受け取りの場合のみ)
以上で、日本の手続きは完了です。ハーグ条約によって、日本の外国大使館・領事館での認証は不要です。外国に渡航して、アポスティーユの付いている認証文書を提出します。 |
|
| 提出先が加盟国でない場合 |
STEP1 市区町村役場
以上で、日本の手続きは完了です。 |
※最新情報は、各法務局、公証役場に確認が必要です。
国際結婚に関して当事務所にできること
当事務所は、入国管理局に在留許可申請等ができる申請取次の資格を持つ行政書士として、国際結婚の相手を日本に呼び寄せたい、さらに日本で子供が生まれた等の国際結婚の場面で必要となってくる在留許可申請の代行をいたします。
また、これから国際結婚をして日本で生活したいという方も、その先の外国人の在留許可申請に必要となる事項を踏まえて適切なアドバイスをさせていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
平日 AM9:00-18:00
電話・メールで御予約いただければ土・日・祝日も対応いたします。
.jpg) 042-595-6071
042-595-6071