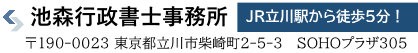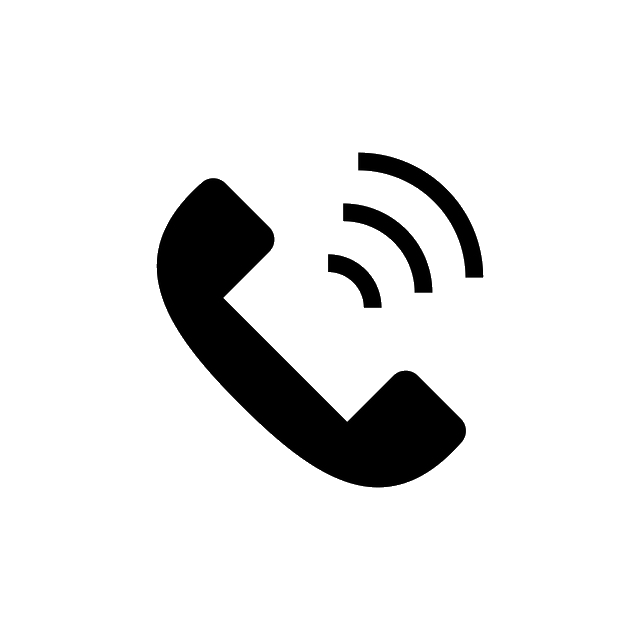���ǖ@�̊�b�m��
�o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�i���ǖ@�j�́A���{�ɓ����܂��͏o������S�Ă̐l�̏o�����Ɠ��{�ɍݗ�����S�Ă̊O���l�̍ݗ��̌����ȊǗ���}��A��̔F��葱�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B���̂��߁A���ǖ@�́A�ݗ����i���x��݂��Ă��܂��B
���̋L���ł́A�o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�i���ǖ@�j�̊�b�m���Ƃ��čݗ����i���x�A���i�r�U�j�A�u�����v�Ɓu�㗤�v�ɂ��Ă�������Ă��܂��B���ꂩ��ݗ����i����肽���l���Ă���O���l�₻�̂��Ƒ��A�O���l���ٗp�������Ƃ��l���̕����ɖ𗧂��e�ƂȂ��Ă��܂��B
�p�X�|�[�g�ƍ��i�r�U�j�̖����`�����Ə㗤�̈Ⴂ�`�@
�ŏ��ɓ��ǖ@�i�o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�j�Ɋ�Â��㗤�葱�����ȒP�ɐ������܂��B
���ǖ@��A�u�����v�Ɓu�㗤�v�ƂQ�̊T�O�ŕ�����Ă��܂��B
�@�����E�E�E�O���l�����{�̗̈�i�C��A���j�ɗ������邱�ƁB
�@�㗤�E�E�E�O���l�����{�̗̓y�ɑ��ݓ���邱�ƁB
�u�����v�Ƃ́A�ȒP�Ɍ����u���{�̗̊C���̋�ɓ��邱�Ɓv�ł��B�ł��̂ŁA�q�D�⍑�ې��̔�s�@�̏�q�́A���{�̗̊C(��)�ɓ��������_�Łu���������v���ƂɂȂ�܂��B
��`�A�C�`�ɒ��������_�ł́A���{�̗̊C(��)�Ɋ��ɓ����Ă����Ԃł��B�܂�A���O�Ɂi�������o������O�Ɂj���{�ɓ������鋖���Ȃ���Εs�@�����Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂���ˁH�@�ł͉��������ē��������O�ɔF�߂��Ă���̂��Ƃ����ƁA�����i�p�X�|�[�g�j�ƍ��i�r�U�j�ɂȂ�܂��B�����Ƃ́A��ʂɂ́A���{�����{�����F�����O�����{�̔��s�����n�q�����̂��ƂŁA���ۗ��s�p�̌����̐g���ؖ����̖����������A���ЁA�����A���N�����A���s�@�ւȂǂ��L�ڂ���A�ʐ^���\�t����Ă�����̂ł��B���i�r�U�j�Ƃ́A�O���̓��{��g�فA�̎��ق����̎҂̏������闷�����^���ł���A���{���ւ̓����ɗL���ł����āA�^���鍸�ɋL�������ɂ����āA���̊O���l�̓��{�ւ̓�������эݗ��������x���Ȃ����Ƃf�����|�̕\���i��j�ł��B
�]���āA���O�Ɂi�������o������O�j�Ɂu�L���ȗ����i�p�X�|�[�g�j�v���擾���A���i�r�U�j��K�v�Ƃ��Ȃ��ꍇ�������āA���{�̍݊O���قɂ����ė����ɍ��i�r�U�j���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł��B
�������A�����i�p�X�|�[�g�j�ƍ��i�r�U�j�������Ă��A�܂��㗤�͂ł��܂���B�����i�p�X�|�[�g�j�ƍ��i�r�U�j�́A��`�i�C�`�j�œ����R�����邽�߂ɕK�v�ƂȂ���̂ł����āA�㗤��ۏ������̂ł͂Ȃ��̂ł��B�ł��̂ŁA��`�A�C�`�ɂ����āA�����R�����ɏ㗤�\�������܂��B���{�ɏ㗤���邽�߂ɂ́A��`�A�C�`�œ����R�����ɂ��㗤�R�����āA������������ɏ㗤���́u�؈�v���Ȃ���Ȃ�܂���B
�����ؑ��ݖƏ��[�u�̑ΏۂɊY�����鍑�̕��͍��i�r�U�j�͕s�v�ł��B
���ؖƏ����ɂ��ẮA�u���ؖƏ����v�̃y�[�W�ʼn�����Ă��܂��B
��`�A�C�`�ɓ������ď㗤�R������i�K�ł́A�ꉞ�A���̏�ɂ͋���̂ł����u�㗤�v�Ƃ͂Ȃ�܂���B�㗤�R����ʂ��Ďn�߂ď㗤�ƂȂ�܂��B
���i�r�U�j�́A�㗤�A�؍���ۏ�����̂ł͂Ȃ��A�㗤���̂��߂̏����̈�ɂ����܂���B�㗤�R���̌��ʁA�㗤���ێ��R�ɓ����邱�Ƃ����o�����悤�ȏꍇ�́A�㗤�͋�����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
���i�r�U�j�́A�㗤�R���������_�Ŏg�p�ς݁i���j�Ƃ���A�O���l�����{�ɏ㗤���A���{�ɑ؍݂ł��鍪���́u�㗤���v�ɂȂ�܂��B
�i���j�����r�U�́A�L�����Ԗ����܂Ŏg�p�ς݂Ƃ͂Ȃ�܂���B
�⑫�ł����A��`�A�C�`�̓����R���ł́A���ۂɍs����̂͏㗤�R���ł��B���ʂ͏㗤�R���Ƃ͌��킸�ɓ����R���ƌ����Ă��邩�Ǝv���܂����E�E�E�B
�Ȃ��A�����Ə㗤�Ƃɕ����čl����K�v������̂��H�Ƌ^��Ɏv�������������Ǝv���܂��B
�����A�����Ƃ����T�O���������A�㗤�Ƃ����T�O�������Ƃ�����A��s�@���C��ɂ��鎞�_�œ������Ă��܂��̂ŁA�������ł́A���{�����ɂ���������R���Ƃ������̂��ł��܂���ˁB�܂��㗤�̊T�O���������A�����Ƃ����T�O�������Ƃ�����ǂ��ł��傤�B�㗤�R���͏㗤�̎��_�ł�����Ƃł���̂ł����A���{�̗̊C�ɕs�@�ɓ������O���l�͊C��ۈ������s�@�����őΏ�����̂�����Ȃ��Ă��܂��܂��B�C���痤�Ɂu�㗤�v����܂ʼn����Ώ��ł��Ȃ��킯�ł�����B���̂悤�Ȏ������悤�ł��B
�p�X�|�[�g�ƍ��i�r�U�j�̖����̂܂Ƃ�
�����i�p�X�|�[�g�j
�����i�p�X�|�[�g�j�Ƃ́A��ʂɂ́A���{�����{�����F�����O�����{�̔��s�����n�q�����̂��ƂŁA���ۗ��s�p�̌����̐g���ؖ����̖����������A���ЁA�����A���N�����A���s�@�ւȂǂ��L�ڂ���A�ʐ^���\�t����Ă�����̂ł��B
���j���ɂ����A�E���ɔ�������闷�s�ؖ����Ȃǂ�����܂��B�i���ǖ@�Q���T���j
�u�L���ȗ����v�Ƃ́A�ȒP�ɂ����ƁA�u���s������L����҂ɂ��K���ɔ��s����A�U���A�U���Ȃǂ������^���Ȃ��̂ŁA��������O���l�̓��肪�m���ɂ����ɑ������́v�Ƃ���Ă��܂��B
���i�r�U�j
���i�r�U�j�Ƃ́A�O���̓��{��g�فA�̎��ق����̎҂̏������闷�����^���ł���A���{���ւ̓����ɗL���ł����āA�^���鍸�ɋL�������ɂ����āA���̊O���l�̓��{�ւ̓�������эݗ��������x���Ȃ����Ƃf�����|�̕\���i��j�ł��B���i�r�U�j�́A�����܂œ��{���̎��ٓ��ɂ������R�����ւ́u���E�v�i�Љ�j�ł��B���i�r�U�j���̂��̂��A�㗤�A�؍���ۏ�����̂ł͂Ȃ��A�㗤�̂��߂̏����̈�ɂ����܂���B���㗤�R���̌��ʁA�㗤���ێ��R�ɓ����邱�Ƃ����o�����悤�ȏꍇ�́A�㗤�͋�����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B
���i�r�U�j�ɂ́A�O�����A���p���A�A�ƍ��A�ʉߍ��A�Z���؍ݍ��A��Ñ؍ݍ��A���x���E���A��ʍ��؋y�ѓ��荸�̂X��ނ�����܂��B
�i��ʍ��Ƃ́A���w�A�Ƒ��؍݁A�Z�\���K�Ȃǂ��Y�����A���荸�́A���[�L���O�z���f�[�A�A�}�`���A�X�|�[�c�A���{�l�̔z��ғ��Ȃǂ��Y�����܂��B�j
�ݗ����i���x�ɂ���
�ݗ����i���x�́A���{�������O���l�̊������J�e�S���[�ʂɍݗ����i��݂��Ă��܂��B�����āA���̍ݗ����i�ɑΉ����銈�����s���O���l�Ɍ����āA���̓����E�ݗ���F�߂�Ƃ������̂ł��B�㗤�R���ŏ㗤��������ē��{�ɍݗ����邽�߂ɂ́A���ǖ@�ɒ�߂�ꂽ�u�ݗ����i�v��L���Ă��邱�Ƃ��K�v�ł��B��`�A�C�`�̓����R���ōs����u�㗤�R���v�ɂ����āA�����ƍ��̗L�����ƁA�ݗ����i�̊Y�����A�㗤��̓K�����Ȃǂ��R������܂��B�ݗ����i�́A���i�r�U�j�Ƃ͑S���ʂ̎��i�ł��B
�@�ݗ����i�́A�O���l�����{�ɓ������čݗ����邱�Ƃ�F�߂鎑�i�ł��B���{�����ɂ���O���l�́A�K�����炩�́u�ݗ����i�v�������Ă��܂��B�ݗ����i�������Ȃ��O���l�́u�s�@�؍݁v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�@�܂��A�O���l��l�ɂ���̍ݗ����i���F�߂��Ă��āA��l��2�ȏ�̍ݗ����i�������Ƃ͂ł��܂���B
�܂��A�ݗ����i�ɑΉ������ݗ����Ԃ��K����߂��܂��B
�u�������؍݁i3�����ȏ�j�v�̗L�����Ԃ�����u�ݗ����i�v�����O���l�ɂ́A�u�ݗ��J�[�h�v�����s����܂����B
�@���u���ʉi�Z�ҁv�A�u�O���v�A�u���p�v�����ݗ����i�������B
���Ȃ݂ɁA�ό��Ȃǂœ��{��K���O���l�̍ݗ����i�́A�u�Z���؍݁v�ł��B�u�Z���؍݁v�̍ݗ����Ԃ�3�����ȓ��ł��邽�߁A�������؍ݎ҂ɂ͊Y�������A�u�ݗ��J�[�h�v�͔��s����܂���B
�u�ݗ��J�[�h�v�ɂ��ẮA�ݗ��J�[�h�̃y�[�W�ŏڂ���������Ă��܂��̂ŕ����Ă��ǂ݂��������B
�ݗ����i�ɂ́A�u�O���v�C�u���p�v�C�u�����v�C�u�|�p�v�C�u�@���v�C�u�v�C�u���x���E�v�A�u�o�c�E�Ǘ��v�C�u�@���E��v�Ɩ��v�C�u��Áv�C�u�����v�C�u����v�C�u�Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��v�C�u��Ɠ��]�v�C�u���s�v�C�u�Z�\�v�C�u���v�A�u�Z�\���K�v�C�u���������v�C�u�Z���؍݁v�C�u���w�v�C�u���C�v�C�u�Ƒ��؍݁v�C�u���芈���v������܂��B�����R�P�N�S������u����Z�\�v���V���ȍݗ����i�ƂȂ�܂����B
�����̍ݗ����i�ɂ́A���{�ɂ������A�J���\�Ȃ������\�łȂ����́A�㗤�������̂�����������������Ƃ�����܂��B
�㗤�R���ɂ����ẮA�u�㗤�̂��߂̏����v�����Ă��邩�R������܂��B
�㗤�̂��߂̏����́A�����Ǘ��@��V���ɒ�߂��Ă���A�ȉ��̂Ƃ���ł��B�i���ǖ@��V���j
���̏㗤�̂��߂̏����̒��ɁA���ǖ@��́u�ݗ����i�v�ɊY�����邱�Ƃ���߂��Ă��܂��B
���㗤�̂��߂̏�����
�@ �L���ȗ����y�ѓ��{���̎����������������L���ȍ����������Ă��邱��
�A �\���ɌW�銈���i�䂪���ōs�����Ƃ��銈���j���U��̂��̂łȂ�����
�B �䂪���ōs�����Ƃ��銈�����C���ǖ@�ɒ�߂�ݗ����i�̂����ꂩ�ɊY������
���ƁA�܂��A�㗤����̂���ݗ����i�ɂ��ẮA���̊�ɓK�����邱��
�C �؍ݗ\����Ԃ��A�ݗ����Ԃ��߂��{�s�K���̋K��ɓK�����邱��
�D ���ǖ@��T���ɒ�߂�㗤���ێ��R�ɊY�����Ȃ�����
�ό��œ��{�ɑ؍݂���ꍇ�́A�u�Z���؍݁v�̍ݗ����i�ƂȂ�܂��B���̏ꍇ�́A�㗤�R���ɂ����ď㗤���̊�͂���܂���B�L���ȗ����ƍ��i�����K�v�ȏꍇ�j������Ώ㗤�ł��܂��B
���j�㗤���ێ��R�ɊY������ꍇ�͏㗤�͋�����܂���B
�㗤�R���葱���̊T����}�Ŏ����ƈȉ��̂悤�ɂȂ�܂��B
�o���O�ɁA�L���ȗ����ƍ�����B

���{�̓����`�ɂ����ď㗤�\��

�㗤�R��

�㗤����
�ݗ��J�[�h�ɂ���
�ݗ��J�[�h�́A�u�������ɑ؍݂���O���l�݂̂ɑ��Č�t����A�Z���؍ݎ҂�s�@�؍ݎ҂ɂ͌�t����܂���B�ݗ��J�[�h�ɂ́A�A�J�����̗L���A���i�O�����̋��ȂǁA�ٗp�傪���ďA�J�\�ȍݗ����i��L���邩�ǂ������f�ł���悤�ȓ��e�ɂȂ��Ă��܂��B�l���ی�̊ϓ_����K�v�ŏ����̏��ƂȂ��Ă��܂��B�ݗ��J�[�h�͊O���l�z�l�ɂƂ��Ă��A�K�@�ɑ؍݂ł��邱�Ƃ̏ؖ����܂��͋��Ƃ��Ă̖����������ƂɂȂ�܂��B
�ݗ��J�[�h�������Ȃ��҂́A�ȉ��̂Ƃ���ŁA����ȊO�̊O���l�ɑ��ݗ��J�[�h����t����܂��B
���ݗ��J�[�h�������Ȃ��ҁ�
�E3�P���ȉ��̍ݗ����Ԃ����肳�ꂽ��
�E�Z���؍݂̍ݗ��������肳�ꂽ��
�E�O���܂��͌��p�̍ݗ����i�����肳�ꂽ��
�E��L�ɏ�����҂Ƃ��ďȗ߂Œ�߂��
�E�ݗ����i��L���Ȃ���
�E���ʉi�Z�ҁi���ʉi�Z�ҏؖ�������t�j
�ݗ��J�[�h�̌�t
�ݗ��J�[�h����t�����`�ł́A�ό��E�r�W�l�X���̈�ʗp�R���ƍݗ��J�[�h��t�Ώۂ̐R���ƃu�[�X��������Ă��܂��B
�V���`�A���c��`�A�H�c��`�A������`�A����`�A�L����`�A������`�ł͏㗤���ɔ����A�ݗ��J�[�h�����s����鈵���ł��B���̑��̋�`��C�`�ł́A�����Ɍ���ݗ��J�[�h��t�����|���L�ڂ���A�O���l�{�l���A�㗤��Ɏs�����ɋ��Z�n�̓͏o��������ɁA���̋��Z�n���ĂɁA�{�l������X�ւōݗ��J�[�h���X������܂��B
�ݗ��J�[�h�͏펞�g�т���`��������܂��B�i16�Ζ����̎҂͌g�ы`���G�Ə��j
�e��͏o
�P�D�������ݗ��O���l�́A���{�ɏ㗤���ċ��Z�n���߂Ă���14���ȓ��Ɏs�����ɋ��Z�n��͂��o��K�v������܂��B���Z�n��ύX�����ꍇ�����l�ł��B
�͏o�͔C�ӑ㗝�l�A�g�ғ����F�߂��Ă��܂��B
�����Ƃ��āA�ό��Ȃǂ̒Z���؍݂������A3�P�����čݗ�����O���l�́A���Y�s�����ɏZ����L����҂ɂ��ďZ���[���쐬���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
14���ȓ��ɓ͂��Ȃ������ꍇ�⋕�U�̓͏o�͔����K�肪����܂��B
�Q�D�����A���ЁA�n��A���N�����A�����@�ցA�����Ȃǂ̕ύX���������ꍇ�́A14���ȓ��ɒn�������Ǘ��ǂɓ͏o���K�v�ł��B
�ݗ��J�[�h�̗L������
�ݗ��J�[�h�ɂ͗L�����Ԃ�����A�����܂łɍX�V���Ȃ���Ȃ�܂���B
�E�i�Z�҈ȊO���ݗ����Ԗ������܂ŁB�i16�Ζ����̏ꍇ�́A�ݗ����Ԗ�������16�Βa�����̂����ꂩ�������j
�E�i�Z�ҁ���t������N�Z�����V�N���o�߂�����B�i16�Ζ����̏ꍇ�́A16�̒a�����܂Łj
�ݗ��J�[�h�̍Ĕ��s
��t���ꂽ�ݗ��J�[�h��ʑ�������A���������ꍇ�́A�n�������Ǘ��ǂōĔ��s�̎葱�����s���A�V�����ݗ��J�[�h���Ĕ��s���Ă��炢�܂��B
�����A����A�Ŏ����ɂ��ݗ��J�[�h���������ꍇ�́A14���ȓ��ɒn�������Ǘ��ǂōݗ��J�[�h�̍Ĕ��s��t�\�������Ȃ���Ȃ�܂���B
�O���l�Ƃ�
���������O���l�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȑl�������̂ł��傤���H
���Ж@��A���{���Ђ������Ă���Γ��{�l�ł��B
���ǖ@��A�O���l�Ƃ́A�u���{���Ђ������Ă��Ȃ��ҁv�ł��B
�]���āA�u�����Ўҁv�͊O���l�ł����A���{���Ђ��܂ށu�d���Ўҁv�́A���{���Ђ�L���Ă���̂œ��{�l�ł��B
���{���Ђ��擾�ł���ꍇ�Ƃ́H
���{���Ђ��擾�ł���ꍇ�́A���Ж@�ɋK�肳��Ă��܂��B
���Ж@�@�i�����j
�i�o���ɂ�鍑�Ў擾�j
��Q��
�q�́A���̏ꍇ�ɂ́A���{�����Ƃ���B
��@�o���̎��ɕ��܂��͕ꂪ���{�����ł���Ƃ�
��@�o���O�Ɏ��S�����������S�̎��ɓ��{�����ł������Ƃ�
�O�@���{�Ő��܂ꂽ�ꍇ�ɂ����āA���ꂪ�Ƃ��ɒm��Ȃ��Ƃ��A���͍��Ђ�L���Ȃ��Ƃ�
�i�F�m���ꂽ�q�̍��Ђ̎擾�j
��R��
�����͕ꂪ�F�m�����q�œ�\�Ζ����̂��́i���{�����ł������҂������j�́A�F�m�����������͕ꂪ�q�̏o���̎��ɓ��{�����ł������ꍇ�ɂ����āA���̕����͕ꂪ���ɓ��{�����ł���Ƃ��A���͂��̎��S�̎��ɓ��{�����ł������Ƃ��́A�@����b�ɓ͂��o�邱�Ƃɂ���āA���{�̍��Ђ��擾���邱�Ƃ��ł���B
�Q�@�O���̋K��ɂ��͏o�������҂́A���̓͏o�̎��ɓ��{�̍��Ђ��擾����B
�i�A���j
��S��
���{�����łȂ��ҁi�ȉ��A�u�O���l�v�Ƃ����j�́A�A���ɂ���āA���{�̍��Ђ��擾���邱�Ƃ��ł���B
�Q�@�A��������ɂ́A�@����b�̋��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����F
���{�l�̕�̏ꍇ�́A�����O�ɂ��q�ǂ��̏ꍇ�ł����Ă��A�o���Ɠ����ɓ��{���Ђ��擾���܂��B
���{�l�̕����琶��F�m�i���܂ꂽ��ɔF�m���邱�Ɓj�����ꍇ�A�o�����_�ɂ����Ă͕��Ɩ@����̐e�q�W�����݂��Ă��Ȃ����߁A�o�����_�œ��{���Ђ��擾���邱�Ƃ͂ł��܂���B
���̏ꍇ�A�͏o�ɂ���ē��{�̍��Ђ��擾���邱�Ƃ��ł��܂��B
�َ��F�m�i���܂��O�ɔF�m����邱�Ɓj�����ꍇ�ɂ́A�o�����ɂ����Ė@����̐e�q�W���������Ă���̂ŁA�o���Ɠ����ɓ��{���Ђ��擾���܂��B
�y�O���ŏo�������ꍇ�̍��Ђɂ��āz
���{�́A���܂ꂽ�����ǂ��ł��邩�Ɋւ�炸�A�����W�ɂ���č��Ђ����肷��u������`�i���ꗼ�n������`�j�v���̗p���Ă��܂��B
�A�����J��J�i�_�Ȃǂ́A���e�̍��ЂɊW�Ȃ��A���܂ꂽ���ɂ���č��Ђ����肷��u�o���n��`�i��������傤�����ガ�j�v���̗p���Ă��܂��B
���̂��߁A�A�����J��J�i�_�Ȃǂ̏o���n��`�̍��ŁA�e�����{�l�ł���q�ǂ������܂ꂽ�ꍇ�ɂ́A�o���ɂ���ē��{���ЂƊO���Ђ̗������擾���邱�ƂɂȂ�A�u��d���Џ�ԁv�ɂȂ�܂��B
���{�͓�d���Ђ�F�߂Ă��炸�A��d���ЂƂȂ����ꍇ�ɂ́A���܂ꂽ������3�����ȓ��Ɂu�o���́v�ƂƂ��Ɂu���З��ہv�̓͏o���o����K�v������܂��B
������o���Ȃ��ł���ƁA���{���Ђ͎����܂��B
���З��ۂ������ꍇ�ɂ́A22�܂łɂǂ��炩�̍��Ђ�I�����܂��B
���j���@�����ɂ��A���l�N��P�W�ɂȂ������Ƃ���A���Ђ̑I����18�܂łɕύX����܂����B
���Ȃ݂ɁA
�����ꗼ�n������`���̗p���Ă��鍑
�^�C�A�����A�؍��A�f���}�[�N�A�g���R�A�i�C�W�F���A�A�m���E�F�[�A�n���K���[�A�t�B���s���ȂǁB
�����n�D�挌����`���̗p���Ă��鍑
�A���u���A�M�A�A���W�F���A�A�C���N�A�C�����A�C���h�l�V�A�A�G�W�v�g�ȂǁB
�����n������`�����A�����t���ŏo���n��`���̗p���Ă��鍑
�C�M���X�A�I�[�X�g�����A�A�I�����_�A�h�C�c�A�t�����X�A���V�A�ȂǁB
���o���n��`���̗p���Ă��鍑
�A�����J�A�J�i�_�A�u���W���A�A�C�������h�ȂǁB
�ł��B
�ݗ����i�ɂ���
�ݗ����i�ɂ́A�A�J�̉ہA�㗤����̗L���ɂ��A�ȉ��̂悤�ɕ��ނ���܂��B
�y�P�z�A�J�n���i
| �A�J�� | �㗤��L�� | �ݗ����i | |
| �A�J�s�� | �㗤����Ȃ� | �u���������v�C�u�Z���؍݁v�C�u���芈���v�̈ꕔ | |
| �㗤������� | �u���w�v�C�u���C�v�C�u�Ƒ��؍݁v | ||
|
�Ɩ�����̏A�J�� |
�㗤����Ȃ� | �u�O���v�C�u���p�v�C�u�����v�C�u�|�p�v�C�u�@���v�C�u�v�C�u���芈���v�̈ꕔ | |
| �㗤������� |
�u���x���E�i�P���j�v,�u�o�c�E�Ǘ��v�C |
||
�y�Q�z�g���n���i
�@�@�@���@�������ɏA�J��
�u�i�Z�ҁv�A�u���{�l�̔z��ғ��v�A�u�i�Z�҂̔z��ғ��v�A�u��Z�ҁv�A�u���ʉi�Z�ҁv
�ݗ����i�F��ؖ����Ƃ�
�O������̌ĂъA�܂�O���ɍݏZ���Ă���O���l����{�ɌĂɊ����A�Ƃ����ꍇ�ɂ́A�ݗ����i�F��ؖ������擾���܂��B
���ǖ@�́C�O���l���u�Z���؍݁v�ȊO�̍ݗ����i�ʼn䂪���ɏ㗤���悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́C�\���Ɋ�Â��@����b�����炩���ߍݗ����i�Ɋւ���㗤�����̓K������R�����C���̌��ʁC���Y�����ɓK������ꍇ�ɂ��̎|�̏ؖ�������t�ł��邱�Ƃ��߂Ă��܂��i�ݗ����i�F��ؖ�����t�\���j�B
���̌�t����镶�����ݗ����i�F��ؖ����Ƃ����܂��B���̍ݗ����i�F��ؖ������x�́C�����R���葱�̊ȈՁE�v�����ƌ�������}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă��܂��B
���ǂɍݗ����i�F��ؖ����̐\�����s���̂́A�擾�������ݗ����i�ɂ���ĈႢ�܂����A������ɂ��Ă����{�ݏZ�̕����A�㗝�l�Ƃ��Đ\������葱���ɂȂ�܂��B�A�J�r�U�ł���A�ٗp�悪�A�g���n�̌����r�U�Ȃǂł͐e���̕����㗝�l�ƂȂ邱�Ƃ��ł��܂��B
�O���l�����{�ɏ㗤�����ʓI�ȕ��@�ό��E���p�r�U�ɂ��Z���؍݂̏ꍇ�A�ݗ����i�F��ؖ����ɂ�钆�����̍ݗ����i�̏ꍇ�ƍē������Ă���ꍇ������܂��B
�P�D�u�Z���؍݁v�̍ݗ����i�ŏ㗤
���ؖƏ����̊O���l���@����������`�A�C�`�ŏ㗤���\���B
���ؖƏ����ȊO�̊O���l������������`�A�C�`�ō�������������ď㗤���\���B
�Q�D�u�Z���؍݁v�ȊO�̍ݗ����i�ŏ㗤
���ؖƏ����̊O���l�܂��͍��ؖƏ����ȊO�̊O���l�������
�����Ǘ��ǂɁu�ݗ����i�F��ؖ�����t�\���v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�ݗ����i�F��ؖ�����Y�t���āA�O���̓��{���قɍ��ؔ����\��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�����������ƍݗ����i�F��ؖ�������āA����������`�A�C�`�ŏ㗤���\���B
�R�D�ē������Ă���ꍇ
���łɍݗ����i�������Ă���O���l���A���{���o�����čēx�A���{�ɓ�������ꍇ�́A�ē������؈������������āA����������`�A�C�`�ŏ㗤���\�����܂��B
�i�݂Ȃ��ē��������܂݂܂��j
�ݗ����i�ύX���Ƃ�
�ݗ����i�̕ύX�Ƃ́C�ݗ����i��L����O���l���ݗ��ړI��ύX���ĕʂ̍ݗ����i�ɊY�����銈�����s�����Ƃ���ꍇ�ɁC�@����b�ɑ��čݗ����i�̕ύX���\�����s���C�]���L���Ă����ݗ����i��V�����ݗ����i�ɕύX���邽�߂ɋ����邱�Ƃ������܂��B
���̎葱�ɂ��C�䂪���ɍݗ�����O���l�́C���ɗL���Ă���ݗ����i�̉��ł͍s�����Ƃ��ł��Ȃ����̍ݗ����i�ɑ����銈�����s�����Ƃ���ꍇ�ł��C�䂪�����炢������o�����邱�ƂȂ��ʂ̍ݗ����i��������悤�\�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�i��F���w����Z�p�A�l���m���E���ۋƖ����ւ̕ύX�Ȃǁj
�ݗ����i�X�V���Ƃ�
���݂̍ݗ����Ԃ��āA�����������{�ɍݗ����悤�Ƃ���ꍇ�Ɏ�ݗ����ԉ����̋��̂��Ƃł��B
�ݗ����i��L���čݗ�����O���l�́C�����Ƃ��ĕt�^���ꂽ�ݗ����ԂɌ����ĉ䂪���ɍݗ����邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂȂ��Ă���̂ŁC�Ⴆ�C�㗤�����ɍۂ��ĕt�^���ꂽ�ݗ����Ԃł́C�����̍ݗ��ړI��B���ł��Ȃ��ꍇ�ɁC��������o�����C���߂č����擾���C�������邱�ƂƂȂ�ƊO���l�{�l�ɂƂ��đ傫�ȕ��S�ƂȂ�܂��B
�����ŁC���ǖ@�́C�@����b���䂪���ɍݗ�����O���l�̍ݗ������������F�߂邱�Ƃ��K���Ɣ��f�����ꍇ�ɁC�ݗ����Ԃ��X�V���Ă��̍ݗ��̌p�����\�ƂȂ�葱���߂Ă��܂��B
���i�O�������Ƃ�
���{�ɍݗ�����O���l�́A�A�J�◯�w�ȂǓ��{�ōs�������ɉ����ċ����ꂽ�����ȊO�ɁC���������Ƃ��^�c���銈�����͕�V���銈�����s�����Ƃ���ꍇ�ɂ́A���炩���߁u���i�O�����v�̋����Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B
�i��F���w����Ƒ��؍݂̎�w���A���o�C�g������ꍇ�́A���̋����K�v�ł��B�j�@
�P���J���͎��i�O�����Ƃ��Ă͌����A������܂��A��O�I�ɁA���w�A���������A�Ƒ��؍݁A�ꕔ�̓��芈���̎��i�̏ꍇ�́A���̐���������܂����A�P���J���ł����Ă���I�ɋ�����܂��B�������A�u�{���̍ݗ��ړI�̊����̐��s��W���Ȃ��͈͓��v�ł��邱�ƂƂ̗v��������܂��B
�ݗ����i�擾���Ƃ�
�ݗ����i�̎擾�Ƃ́C���{���Ђ̗��E��o���Ȃǂɂ��A���ǖ@�ɒ�߂�㗤�̎葱���o�邱�ƂȂ����{�ɍݗ����邱�ƂƂȂ�O���l�̕����C���̎��R���������������������60�����ē��{�ɍݗ����悤�Ƃ���ꍇ�ɕK�v�Ƃ����ݗ��̋��ł��B
���̎��R�̐����������璼���ɍݗ�����K�v�Ƃ���̂ɂ͖��������邱�Ƃ�A�����ݗ��̈ӎv�̂Ȃ��ꍇ������܂��B�����ŁC�����̎��R�̐�����������60���܂ł͈��������ݗ����i��L���邱�ƂȂ��ݗ����邱�Ƃ��F�߂��Ă��܂��B
�ē������Ƃ�
�ē������Ƃ́C���ɓ��{�ɍݗ�����O���̕����ꎞ�I�ɏo�����čē������悤�Ƃ���ꍇ�ɁC�����E�㗤�葱���ȗ������邽�߂ɖ@����b���o���ɐ旧���ė^�����鋖�ł��B�i�����F�K�����{�o���O�Ɏ擾����K�v������܂��j
�ē������i�݂Ȃ��ē��������܂݂܂��B�j�����ɏo�������ꍇ�ɂ́C���̊O���̕����L���Ă����ݗ����i�y�эݗ����Ԃ͏��ł��Ă��܂��܂��̂ŁC���{�ɍē������悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́C���̓����ɐ旧���ĐV���ɍ����擾������ŁC�㗤�\�����s���㗤�R���葱���o�ď㗤�����Ȃ���Ȃ�܂���B
����ɑ��C�ē������i�݂Ȃ��ē��������܂݂܂��B�j�����ꍇ�́C�ē������̏㗤�\���ɓ�����C�ʏ�K�v�Ƃ���鍸���Ə�����܂��B
�i�Z���Ƃ�
�i�Z���́C�ݗ����i��L����O���l���i�Z�҂ւ̍ݗ����i�̕ύX����]����ꍇ�ɁC�@����b���^���鋖�ł���C�ݗ����i�ύX���̈��ł��B
���ŏ�����i�Z���̎��i�œ��{�ɏ㗤���邱�Ɓi�C�O����̌Ăъj�͂���܂���B
�ݗ����i�u�i�Z�ҁv�́C�ݗ������C�ݗ����Ԃ̂��������������Ȃ��Ƃ����_�ŁC���̍ݗ����i�Ɣ�ׂđ啝�ɍݗ��Ǘ����ɘa����܂��B���̂��߁C�i�Z���ɂ��ẮC�ʏ�̍ݗ����i�̕ύX�����T�d�ɐR������Ă���C��ʂ̍ݗ����i�̕ύX���葱�Ƃ͓Ɨ������K�肪���ɐ݂����Ă��܂��B
�܂Ƃ�
�������ł����ł��傤���H���ǖ@�̊�{�I�ȕ����͂��̋L���ł����������������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�e���ɂ��Ă͏ڍL�������J���Ă��܂��̂ŁA�������Č䗗���������B
�Q�l�L��
 �Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��̃r�U�擾���@
�Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��̃r�U�擾���@
�܂��͂��C�y�ɂ����k�������B
�����@AM9:00-18:00
�d�b�E���[���Ō�\��������Γy�E���E�j�����Ή��������܂��B
�@.jpg) 042-595-6071�@
042-595-6071�@