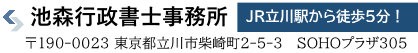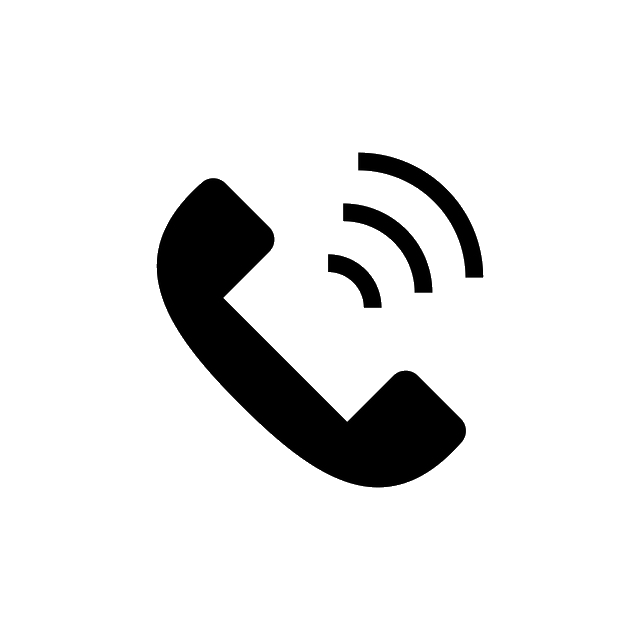�O���l�r�U�i�ݗ����i�j�̋��ɂ���
�ݗ����i�Ƃ́A�O���l�����{�ɑ؍݂��鍪���ƂȂ���̂ŁA�u�o�����Ǘ��y�ѓ�F��@�v�ɒ�߂銈�����s�����Ƃ��ł��鎑�i�ł��B�O���l�����{�ݗ����ɍs�����Ƃ��ł��銈���͈̔͂́A���̍ݗ����i�ɉ����Ă��ꂼ���߂��Ă��܂��B�����Ƃ��āA�O���l�͂��̍ݗ����i�ɔF�߂��Ă���ȊO�̎��������������邱�Ƃ͂ł��܂���B
���u���i�O�����̋��v���擾����ꍇ�������܂��B
���{�ɓ������ݗ�����O���l�́A�����Ƃ��āA�o�����`�ɂ����ď㗤�����A���̍ۂɌ��肳�ꂽ�ݗ����i�ɂ��A�ݗ����邱�ƂɂȂ�܂��B�������ݗ����Ԃ͍ݗ����i���ƂɁA�������A5�N�A3�N�A1�N�A���N�A3�����A30���A15���Ȃǂƒ�߂��Ă��܂��B
�ݗ����i�������Ȃ��œ��{�����ɂ���O���l�́u�s�@�؍݁v�ƂȂ�܂��B�܂��A�ݗ����i�́A��l�łЂƂ̎��i�̂ݗ^�����A2�ȏ�̍ݗ����i�͕t�^����܂���B
�Ⴆ�A�ό��Ȃǂœ��{��K���O���l�̍ݗ����i�́A�ݗ����Ԃ�3�����ȓ��́u�Z���؍݁v�Ƃ����ݗ����i�ɂȂ�܂��B
�ݗ����i�̎��
�ݗ����i�́A�R�Q�i�ł��ׂ���������ƂR�W�j�ɋ敪�ł���̂ł����A��ނ̐��������ł��B���{�ɍݗ����悤�Ƃ���Ƃ��A�ǂ̍ݗ����i���K�v�Ȃ̂��H�f����̂͗e�Ղł͂���܂���B�ݗ����i�́A�傫���S�ɋ敪�ł��܂��B
(1)�y�A�J�n���i�z�A�J�ł���Ǝ�ɐ������������
�@�u�Z�\�v�A�u�Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��v���A�����͂�����ɊY�����܂��B
(2)�y�g���n���i�z�A�J�ł���Ǝ�Ɋ�{�I�ɐ������Ȃ�����
�@�u���{�l�̔z��ғ��v�̐g���n���i������ɊY�����܂��B
(3)�A�J�͌ʂɎw�肳�ꂽ�����̂ݔF�߂������
�@�u���芈���v���Y�����܂��B
(4)�A�J���F�߂��Ȃ�����
�@�u���w�v�A�u�Z���؍݁v�����Y�����܂��B
�@�@�� ���i�O�����������ꍇ�́C���͈͓̔��ŏA�J���F�߂��܂��B
���@�A�J�n���i�́u����Z�\1���v�A�u����Z�\2���v�͕���31�N4������X�^�[�g�����V���x�ł��B
�A�J���F�߂���ݗ����i�i�A�J��������j
| �ݗ����i | �{�M�ɂ����čs�����Ƃ��ł��銈�� | ��̗� |
| �O�� | ���{�����{���ڎ�O�����{�̊O���g�ߒc�Ⴕ���͗̎��@�ւ̍\�����A���Ⴕ���͍��ۊ��s�ɂ��O���g�߂Ɠ��l�̓����y�іƏ�����Җ��͂����̎҂Ɠ���̐��тɑ�����Ƒ��̍\�����Ƃ��Ă̊��� | ��g�A���g���̊O��E�� |
| ���p | ���{�����{�̏��F�����O�����{�Ⴕ���͍��ۋ@�ւ̌����ɏ]������Җ��͂��̎҂Ɠ���̐��тɑ�����Ƒ��̍\�����Ƃ��Ă̊����i���̕\�̊O���̍��̉����Ɍf���銈���������B�j |
�E�O�����{����h�������ҁi�O���������j |
| ���� | �{�M�̑�w�Ⴕ���͂���ɏ�����@�֖��͍������w�Z�ɂ����Č����A�����̎w�����͋�������銈�� | ��w�����A�������w�Z���� |
| �|�p | ���������y�A���p�A���w���̑��̌|�p��̊����i�u���s�v�Ɍf���銈���������B�j | ��ȉƁA��ƁA������ |
| �@�� | �O���̏@���c�̂ɂ��{�M�ɔh�����ꂽ�@���Ƃ̍s���z�����̑��̏@����̊��� | �O���̏@���c�̂���h�������_���A�m���A�i���A�鋳�t�A�q�t�A�_�� |
| �� | �O���̕@�ւƂ̌_��Ɋ�Â��čs����ނ��̑��̕�̊��� | �V���L�ҁA�J�����}�� |
| ���x���E�P�� | ���x�̐��I�Ȕ\�͂�L����l�ނƂ��Ė@���ȗ߂Œ�߂��ɓK������҂��s�����̃C����n�܂ł̂����ꂩ�ɊY�����銈���ł��āA�䂪���̊w�p�������͌o�ς̔��W�Ɋ�^���邱�Ƃ������܂����� | |
|
�C�@�@����b���w�肷��{�M�̌����̋@�ւƂ̌_��Ɋ� |
�y���x�w�p��������z |
|
|
���@�@����b���w�肷��{�M�̌����̋@�ւƂ̌_��Ɋ� |
�y���x���E�Z�p����z |
|
|
�n�@�@����b���w�肷��{�M�̌����̋@�ւɂ����Ėf�� |
�y���x�o�c�E�Ǘ�����z |
|
| ���x���E�Q�� | �O���Ɍf���銈�����s���҂ł��āA���̍ݗ����䂪���̗��v�Ɏ�������̂Ƃ��Ė@���ȗ߂Œ�߂��ɂ��̂��s�����Ɍf���銈�� | �|�C���g�̍��v���V�O�_�ȏ�ŁA���x���E�P���̎��i�łR�N�ȏ�ݗ����Ă��铙�B |
|
�C�@�{�M�̌����̋@�ւƂ̌_��Ɋ�Â��Č����A������ |
||
|
���@�{�M�̌����̋@�ւƂ̌_��Ɋ�Â��Ď��R�Ȋw���� |
||
|
�n�@�{�M�̌����̋@�ւɂ����Ėf�Ղ��̑��̎��Ƃ̌o�c |
||
|
�j�@�C����n�܂ł̂����ꂩ�̊����ƕ����čs����̕\ |
||
| �o�c�E�Ǘ� | �{�M�ɂ����Ėf�Ղ��̑��̎��Ƃ̌o�c���s�����͓��Y���Ƃ̊Ǘ��ɏ]�����銈���i���̕\�́u�@���E��v�Ɩ��v�Ɍf���鎑�i��L���Ȃ���Ζ@����s�����Ƃ��ł��Ȃ����ƂƂ���Ă��鎖�Ƃ̌o�c�Ⴕ���͊Ǘ��ɏ]�����銈���������B�j |
�E�o�c�ҁA�Ǘ��E�� |
| �@���E��v�Ɩ� | �O���@�����ٌ�m�A�O�����F��v�m���̑��@���㎑�i��L����҂��s�����ƂƂ���Ă���@�����͉�v�ɌW��Ɩ��ɏ]�����銈�� | ���{�@��ٌ̕�m�A�O���@�����ٌ�m�A���{�@��̌��F��v�m�A�O�����F��v�m�� |
| ��� | ��t�A���Ȉ�t���̑��@���㎑�i��L����҂��s�����ƂƂ���Ă����ÂɌW��Ɩ��ɏ]�����銈�� | ��t�A���Ȉ�t�A��t�A�ی��t�A���Y�w�A�Ō�t |
| ���� | �{�M�̌����̋@�ւƂ̌_��Ɋ�Â��Č������s���Ɩ��ɏ]�����銈���i�u�����v�Ɍf���銈���������B�j | ��w���ȊO�̎������A���������Ŏ����A�����A�������ɏ]������� |
| ���� | �{�M�̏��w�Z�A���w�Z�A�����w�Z�A��������w�Z�A���ʎx���w�Z�A��C�w�Z���͊e��w�Z�Ⴕ���͐ݔ��y�ѕҐ��Ɋւ��Ă���ɏ����鋳��@�ւɂ����Č�w���炻�̑��̋�������銈�� | ���w�Z�A���w�Z�A�����w�Z�A��C�w�Z���̋���� |
|
�Z�p�E�l���m���E |
�{�M�̌����̋@�ւƂ̌_��Ɋ�Â��čs�����w�A�H�w���̑��̎��R�Ȋw�̕���Ⴕ���͖@���w�A�o�ϊw�A�Љ�w���̑��̐l���Ȋw�̕���ɑ�����Z�p�Ⴕ���͒m����v����Ɩ����͊O���̕����Ɋ�Ղ�L����v�l�Ⴕ���͊���K�v�Ƃ���Ɩ��ɏ]�����銈���i�u�����v�̍��A�u�|�p�v�̍��y�сu�v�̍��Ɍf���銈�����тɁu�o�c�E�Ǘ��v�̍�����u����v�̍��܂ŁA�u��Ɠ��]�v�̍��y�сu���s�v�̍��Ɍf���銈���������B�j | �R���s���[�^�Z�t�A�o�C�I�e�N�m���W�[�Z�t�A�ʖ�ҁA�|��ҁA��w�w���ҁA�̔��Ɩ��A�C�O����Ɩ����ɏ]������E�� |
| ��Ɠ��]�� | �{�M�ɖ{�X�A�x�X���̑��̎��Ə��̂�������̋@�ւ̊O���ɂ��鎖�Ə��̐E�����{�M�ɂ��鎖�Ə��Ɋ��Ԃ��߂ē]���ē��Y���Ə��ɂ����čs�����̕\�́u�Z�p�v�̍����́u�Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��v�̍��Ɍf���銈�� | ���Ԋ�ƁA���ЁA���c�A�e��c�́A�O����ƁA�O���n��Ɠ��̊�Ɠ��]�� |
| ��� | �{�M�̌����̋@�ւƂ̌_��Ɋ�Â��ĉ�앟���m�̎��i��L����҂���얔�͉��̎w�����s���Ɩ��ɏ]�����銈�� | ���{�̉�앟���m�̎��i�擾�� |
| ���s | �����A���|�A���t�A�X�|�[�c���̋��s�ɌW�銈�����͂��̑��̌|�\�����i���̕\�́u�o�c�E�Ǘ��v�̍��Ɍf���銈���������B�j | ���y�ƁA���x�ƁA�o�D�A�T�[�J�X�c���A���|�ƁA�E�ƃX�|�[�c�ƁA�e���r�E�R�}�[�V�����o������� |
| �Z�\ | �{�M�̌����̋@�ւƂ̌_��Ɋ�Â��čs���Y�Ə�̓���ȕ���ɑ�����n�������Z�\��v����Ɩ��ɏ]�����銈�� |
�E�����l�i���m�����A |
| �Z�\���K�P�� | ���̃C���̓��̂����ꂩ�ɊY�����銈�� | |
|
�C�@�O���l�̋Z�\���K�̓K���Ȏ��{�y�ыZ�\���K���̕� |
�E�����P�N�ڂ̋Z�\���K�� |
|
|
���@�Z�\���K�@�攪���ꍀ�̔F����������ɋK�� |
�E�����P�N�ڂ̋Z�\���K�� |
|
| �Z�\���K�Q�� | ���̃C���̓��̂����ꂩ�ɊY�����銈�� | |
|
�C�@�Z�\���K�@�攪���ꍀ�̔F����������ɋK�� |
�E�����Q,�R�N�ڂ̋Z�\���K�� |
|
|
���@�Z�\���K�@�攪���ꍀ�̔F����������ɋK�� |
�E�����Q��R�N�ڂ̋Z�\���K�� |
|
| �Z�\���K�R�� | ���̃C���̓��̂����ꂩ�ɊY�����銈�� | |
|
�C�@�Z�\���K�@�攪���ꍀ�̔F����������ɋK�� |
�E�D�ǂȊė��c�̋y�ю��K�� |
|
|
���@�Z�\���K�@�攪���ꍀ�̔F����������ɋK�� |
�E�D�ǂȊė��c�̋y�ю��K�� |
|
| ����Z�\�P�� | ����Y�ƕ���ɑ����鑊�����x�̒m�����͌o����K�v�Ƃ���Z�\��v����Ɩ��ɏ]������� | �ڍׂ͂����� |
| ����Z�\�Q�� | ����Y�ƕ���ɑ�����n�������Z�\��v����Ɩ��ɏ]������� |
�g���E�n�ʂɊ�Â��ݗ����i�i�A�J�B���������Ȃ��j
| �ݗ����i | �{�M�ɂ����ėL����g�����͒n�� | ��̗� |
| �i�Z�� | �@����b���i�Z��F�߂�� | �i�Z����ҁB�����ɐ����͂Ȃ��B |
| ���{�l�̔z��ғ� | ���{�l�̔z��ҎႵ���͓��ʗ{�q���͓��{�l�̎q�Ƃ��ďo�������� | ���{�l�̔z��ҁA���q�A���ʗ{�q�� |
| �i�Z�҂̔z��ғ� | �i�Z�҂̔z��Җ��͉i�Z�ғ��̎q�Ƃ��Ė{�M�ŏo�������̌���������{�M�ɍݗ����Ă���� |
�E�i�Z�҂̔z��ҁA���q�B |
| ��Z�� | �@����b�����ʂȗ��R���l�������̍ݗ����Ԃ��w�肵�ċ��Z��F�߂�� |
�E�@����b�����ʂȁi�l���I�j |
�A�J�̉ۂ͎w�肳��銈���ɂ��ݗ����i
| �ݗ����i | �{�M�ɂ����čs�����Ƃ��ł��銈�� | ��̗� |
| ���芈�� | �@����b���X�̊O���l�ɂ��Ď��̃C����j�܂ł̂����ꂩ�ɊY��������̂Ƃ��ē��Ɏw�肷�銈�� |
�E���[�L���O�z���f�[ |
�A�J�͔F�߂��Ȃ��ݗ����i
�@�� ���i�O�����������ꍇ�́C���͈͓̔��ŏA�J���F�߂��܂��B
| �ݗ����i | �����̓��e | ��̗� |
| �������� | ������Ȃ��w�p��Ⴕ���͌|�p��̊������͉䂪�����L�̕����Ⴕ���͋Z�|�ɂ��Đ��I�Ȍ������s���Ⴕ���͐��Ƃ̎w�����Ă�����C�����銈���i�u���w�v�̍�����u���C�v�̍��܂łɌf���銈���������B�j |
�E�O���̑�w�̋����A���������� |
| �Z���؍� | �{�M�ɒZ���ԑ؍݂��čs���ό��A�ۗ{�A�e���̖K��A���w�A�u�K���͉�ւ̎Q���A�Ɩ��A�����̑������ɗގ����銈�� | �ό��A�e���̖K��A���w�A�u�K�A��ւ̎Q���A�Ɩ��A���� |
| ���w | �{�M�̑�w�A�������w�Z�A�����w�Z�i��������w�Z�̌���ے����܂ށB�j�Ⴕ���͓��ʎx���w�Z�̍������A��C�w�Z�Ⴕ���͊e��w�Z���͐ݔ��y�ѕҐ��Ɋւ��Ă����ɏ�����@�ւɂ����ċ�����銈�� |
�w���A���k�A���u���A�������Ƃ��č݊w���A�w�K����� |
| ���C | �{�M�̌����̋@�ւɂ�������čs���Z�\���̏C�������銈���i�u�Z�\���K�v�̍��̑�ꍆ�y�сu���w�v�̍��Ɍf���銈���������B�j |
�E�O���l�̂��߂̌��C�̑̐��� |
| �Ƒ��؍� | �@�ʕ\��̕\�A��̕\���͎O�̕\�̏㗓�̍ݗ����i�i�u�O���v�A�u���p�v�A�u�Z�\���K�v�y�сu�Z���؍݁v�������B�j�����čݗ�����Җ��͂��̕\�̗��w�̍ݗ����i�����čݗ�����҂̕}�{����z��Җ��͎q�Ƃ��čs������I�Ȋ��� |
�A�J���i�ōݗ�����O���l�� |
�㗤����Ƃ́H
�㗤���ێ��R�Ƃ́C�䂪���ɂƂ��Č��O�q���C���̒����C�����̎��������Q����邨���ꂪ����ƔF�߂�O���l�̓����E�㗤�����ۂ���O���l�̗ތ^���߂����̂ł��B��̓I�ɂ͉��L�̂悤�ȊO���l���䂪���ւ̓��������ۂ���܂��B
�@ �ی��E�q����̊ϓ_����㗤�����ۂ�����
�A �Љ�������ƔF�߂��邱�Ƃɂ��㗤�����ۂ�����
�B �䂪������ދ������������Ɠ��ɂ��㗤�����ۂ�����
�C �䂪���̗��v���͌������Q���邨���ꂪ���邽�ߏ㗤���ۂ�����
�D ���ݎ�`�Ɋ�Â��㗤�����ۂ�����
�㗤�����ۂ���ދ����߂����O���l�́C���₩�ɍ��O�ɑދ����Ȃ���Ȃ�܂���B
�Q�l�L��
 �Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��̃r�U�擾���@
�Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��̃r�U�擾���@
�܂��͂��C�y�ɂ����k�������B
�����@AM9:00-18:00
�d�b�E���[���Ō�\��������Γy�E���E�j�����Ή��������܂��B
�@.jpg) 042-595-6071�@
042-595-6071�@