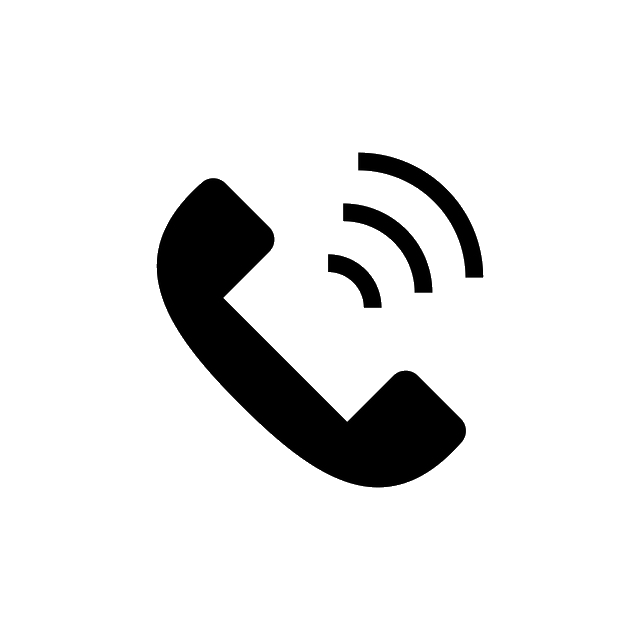就労ビザの活動範囲について
この記事では、就労可能なビザ(在留資格)の活動範囲について解説していきます。
就労するには、企業との雇用契約、給与、労働条件、勤務形態、学歴、実務経験など、就労できるための条件や、いろいろな面で外国人と企業の間での条件を定める必要がありますが、それらにはどのような制約があるのか、そのような疑問をお持ちの方は、一読をお勧めします。
1.就労可能な在留資格
「高度専門職」、「研究」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「技能」、「特定技能」の在留資格においては、「外国人本人と本邦の公私の機関との契約に基づいて行われる活動」であることが求められています。
「本邦の公私の機関」とは以下をいいます。
①国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人
②任意団体(契約当事者としての権利能力がない)
③本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む)、外国の法人
④個人(本邦で事務所、事業所等を有する場合)
2.「契約」の形態
「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。
契約に基づく活動は、本邦において適法に行われるものであることを要します。また、在留活動が継続して行われることが見込まれる必要があります。労働契約の締結に当たっては、使用者は、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を書面で明示しなければならないこととされています。労働契約には、雇用契約のほか、委任契約や請負も含まれます。
3.報酬
「経営・管理」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「介護」、「興行」,「文化活動」、「技能」および「特定技能」の在留資格においては、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」の旨の規定があります。(上陸基準省令、特定技能基準省令)
また、「興行」の在留資格では、月額20万円以上の報酬が要件となっています。(上陸基準省令)
この「日本人と同等額以上の報酬」については以下のとおり、取り扱われます。
1.報酬の月額は、賞与を含め、1年間従事した場合に受ける報酬の12分の1とする。
2.報酬とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含まない。(課税対象となるものを除く)
(注)社会保険制度における報酬の定義とは異なります。
3.役務の提供が本邦内で行われ、その対価として給付を受けている場合は、対価を支給する機関が本邦内にあるかどうかに関わらない。(外国の機関も含まれる)
ただし、従たる業務であって短期間、本邦で活動を行う場合はには、外国の機関が支給する対価はこれに該当しない。
(例:日本へ輸出販売した機器の設置、アフターサービス、会議のための短期間滞在など)
4.常勤の職員とは
「経営・管理」,「興行」,「留学」の在留資格においては、「常勤の職員」に関する規定があります。
常勤の職員とは以下の観点からとらえられます。
1.一定の勤務計画の下に毎日所定の時間中、常時その職務に従事するものであること(休日等を除く)
2.労働時間が週5日以上、年間217日以上で、週30時間以上
3.入社日を起点として、6ケ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した職員に対し、10日以上の年次有給休暇を与えられること
4.雇用保険の被保険者であり、かつ一週間の所定労働時間が30時間以上であること。
(注)短期雇用特例被保険者)いわゆる季節労働者)または日雇労働被保険者は除く。
5.雇用形態として、直接雇用、出向(移籍出向のみ)。
(注)派遣、在籍出向を除く。
5.学歴について
「高度専門職」、「研究」,「教育」及び「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、「大学を卒業」、「これと同等以上の教育を受け」又は「本邦の専修学校の専門課程を修了(告示の用家んい該当する場合に限る)のいずれかが求められます。
1.大学を卒業し」とは、学士又は短期大学学士以上の学位を取得していること
2.大学の専攻科、大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と怒涛である高等専門学校の卒業者
3.当該機関の職員が教員職俸給表(一)の「適用を受ける機関及び設備及びカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関の卒業者
4.学校教育法施行規則第155条第1項第4号に基づき、文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及びこれに相当する外国の教育機関の卒業者
5.職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校を卒業し、終了証明書を交付された者
6.文部科学省編「諸外国の学校教育」において、高等教育機関として位置づけられている機関を卒業した者
7.学校教育法102条第2項に,基づき、大学院への入学(いわゆる飛び入学)が認められた者
6.外国の公的機関及び外国の教育機関の範囲
外国の公的機関は「研修」の上陸基準、外国の教育機関は「興行」、「技能」、「研修」の在留資格に規定があります。
「研修」においては、外国の公的機関又は教育機関で1か月以上かつ160時間以上の非実務研修を実施した場合は、本邦で必要な非実務研修の時間数が緩和されます。
1.外国の公的機関
外国の国または地方公共団体をいう。
(注)中国においては、国家事業単位登記管理局発行の「事業単位法人証書」は、本邦において独立行政法人、公益法人のような組織であるため、「外国の公的機関」には該当しないことに留意が必要です。
2.外国の教育機関
その国・地域における学校教育制度に照らして正規の教育機関として認定されているものであり、かつ原則として義務教育終了後に入学するもの。
7.実務経験について
従事しようとする業務に関する実務経験は、職業活動として従事した期間を言い、教育機関(夜間学部を除く)に所属している間にアルバイト的に従事した期間は含まない。
ただし、上陸基準省令に、教育機関において従事しようとする業務に係る科目を専攻した期間を含む旨の規定がああるものについては、当該機関を含む。
参考記事
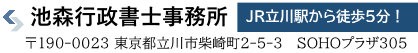


.jpg)