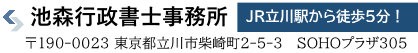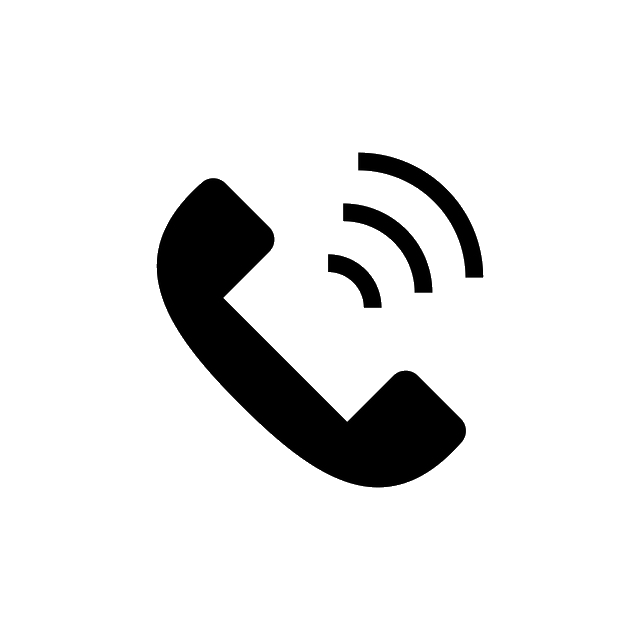�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�ɂ���
���̋L���ł́A�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�ɂ��āA�d���i�����j�̓��e�A���{�ɓ����i�㗤�j���悤�Ƃ���ۂɖ������ׂ��㗤��ɂ��ĉ�����Ă��܂��B���ꂩ��u�o�c�E�Ǘ��v�Ɏ��i�ύX�������ƍl���Ă�����⋤���o�c����O���l���Ăъ����ƍl���Ă����Ƃ̕��ɖ𗧂��e�ƂȂ��Ă��܂��B
�P�D�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�̊������e
�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�Ƃ́A�{�M�ɂ����Ėf�Ղ��̑��̎��Ƃ̌o�c���s�����͓��Y���Ƃ̊Ǘ��ɏ]�����銈���i���̕\�̖@���E��v�Ɩ��̍��̉����Ɍf���鎑�i��L���Ȃ���Ζ@����s�����Ƃ��ł��Ȃ����ƂƂ���Ă��鎖�Ƃ̌o�c���͊Ǘ��ɏ]�����銈���������B�j�B
�Y����Ƃ��ẮC��Ƃ̌o�c�ҁC�Ǘ��҂Ȃǂł��B
��̓I�ɂ́A�O���l�����{�ŋN�Ƃ��Ď��Ƃ��s���ꍇ�A�܂��͓��{��Ƃɓ������Čo�c�Ɍg���ꍇ�A���邢�͓��{�ɂ����Ƃ̊Ǘ��Ɩ����s���ꍇ�Ȃǂɂ����āA�o�c�E�Ǘ��r�U�i�ݗ����i�j���K�v�ƂȂ�܂��B�O���l�����Ȏ��{�ŋN�Ƃ��邱�Ƃ�A�O�����{�ɂ��Ȃ����{��Ƃł̌o�c�Ǘ��Ɍg��邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B
�Ɩ��`�ԂƂ��ẮA�ȉ��̂悤�ȃP�[�X������܂��B
1.���{�ŐV���ȉ�ЂɊO���l����o�����Đݗ����A���̌o�c���s���B
2.���{�̊�Ƃɏo�����āA���̊�Ƃ̌o�c�܂��͊Ǘ��Ɩ����s���B
3.���{�ɊO����Ƃ̎q��Ђ�ݗ����A���̉�Ђ̌o�c�܂��͊Ǘ��Ɩ����s���B
�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�́A�]���A�O���n��Ɓi�O���l�܂��͊O����Ƃ��o���j�ɂ�����o�c�E�Ǘ������Ɍ��肳��Ă��܂������A����26�N�ɓ��n��Ɓi�O���l�܂��͊O����Ƃ��o�����Ă��Ȃ���Ɓj�̌o�c�E�Ǘ��̊������F�߂��Ă��܂��B
�O���l�̐\���҂ɂ��o�����K�������K�v�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�i�������A���̐R���ɂ����ẮA�d�v�Ȕ��f�v�f�ɂȂ�܂��B�j
���Ƃ̌o�c�̊����Ƃ�
���Ƃ̌o�c�̊����Ƃ́A�Ⴆ�A�В��A������A�č��̊������Ӗ����܂����A�č����́A�T�d�ɐR������܂��B
���Ƃ̌o�c���͊Ǘ��Ɏ����I�ɎQ�悷��҂Ƃ��Ă̊����ł��̂ŁC�����ɏA�C���Ă���Ƃ������Ƃ����ł́C���Y�ݗ����i�ɊY��������̂Ƃ͂����܂���B
���s�ϊ����̉ߔ������擾���đ�\������ɏA�C����悤�ȏꍇ�́A�o�c�E�Ǘ����s���Ɣ��f�����\���������ł����A�c�����̖����������擾���Ď�����ɏA�C�����悤�ȏꍇ�́A�o�c���s���Ɣ��f����Ȃ��\��������܂��B
���Ƃ̊Ǘ��ɏ]�����銈��
���Ƃ̊Ǘ��ɏ]�����銈���Ƃ́A���ɑ�����������g�D�̊Ǘ��I�Ɩ��Ƃ���A�����A�H�꒷�A�x�X�����̊������Ӗ����܂��B
�Q�D�����o���E�����o�c
�����Ŏ��Ƃ��N�����������̊O���l�����ꂼ������ɏA�C����悤�ȏꍇ�ɂ́C���ꂼ��̊O���l���]�����悤�Ƃ����̓I�Ȋ����̓��e����C���̍ݗ����i�Y�����y�я㗤��K������R�����邱�ƂƂȂ�܂��B�܂��C�����̊O���l�����Ƃ̌o�c���͊Ǘ��ɏ]������Ƃ����ꍇ�C���ꂼ��̊O���l�̊������u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�ɊY������Ƃ����邽�߂ɂ́C���Y���Ƃ̋K�́C�Ɩ��ʁC���㓙�̏����Ă��C���Ƃ̌o�c���͊Ǘ����̊O���l���s�������I�ȗ��R��������̂ƔF�߂���K�v������܂��B
����27�N�ɁA���̍l���������\����Ă��܂��B���ꂼ��̊O���l�S���ɂ��āC�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�ɊY������Ƃ̔��f���\�Ƃ�����v���́A
�i�P�j���Ƃ̋K�͂�Ɩ��ʓ��̏����Ă��āC���ꂼ��̊O���l�����Ƃ̌o�c���͊Ǘ����s�����Ƃɂ��č����I�ȗ��R���F�߂��邱��
�i�Q�j���Ƃ̌o�c���͊Ǘ��ɌW��Ɩ��ɂ��āC���ꂼ��̊O���l���Ƃɏ]�����邱�ƂƂȂ�Ɩ��̓��e�����m�ɂȂ��Ă��邱��
�i�R�j���ꂼ��̊O���l���o�c���͊Ǘ��ɌW��Ɩ��̑Ή��Ƃ��đ����̕�V�z�̎x�������邱�ƂƂȂ��Ă��邱�Ɠ��̏�������������Ă���ꍇ
�ƂȂ��Ă��܂��B
����
�O���l2�������ꂼ��T�O�O���~�o�����āC�A���G�Ƃ��c�ގ��{���P�O�O�O���~�̉�Ђ�ݗ������B
2���͂��ꂼ��A�ʊ֎葱�E�A�o���Ɩ����̊C�O����y�ѕi���E�ɊǗ��E�i���Ǘ��̐��Ƃł���B
2���͂��ꂼ��̐�含���������ċƖ��f���C�o�c���j�ɂ��ẮC�����o�c�҂Ƃ��č��c���Č��肵�Ă���B
��V�́C���Ǝ��v���炻�ꂼ��̏o���z�ɉ����������Ŏx�����邱�ƂƂȂ��Ă���B
�R�D���̍ݗ����Ƃ̊W
�E�u�@���E��v�Ɩ��v�̍ݗ����i
�ٌ�m�A���F��v�m���ŁA��ƂɌٗp����A���̐��m���������āA�o�c�E�Ǘ��ɏ]������ꍇ�́A�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�ɊY�����܂��B
�u�Ɛ�Ɩ��v�Ƃ��Ė@���Ɩ����v�Ɩ����s���ꍇ�́A�u�@���E��v�Ɩ��v�̍ݗ����i�ɊY�����܂��B
�E�u��Áv�̍ݗ����i
��t�̎��i�����҂��A�a�@�̌o�c�҂Ƃ��Čo�c���銈���́A�u��Áv�ł͂Ȃ��A�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�ɊY�����܂��B
�S�D�㗤��ɂ���
�㗤��ɂ��Ăł����A���{�ɓ����i�㗤�j����ۂ̐\���l�i�O���l�j������1.2.3.�̂�����ɂ��Y�����Ă��邱�Ƃ��K�v�ł��B
1�D�\���ɌW�鎖�Ƃ��c�ނ��߂̎��Ə����{�M�ɑ��݂��邱�ƁB�������A���Y���Ƃ��J�n����Ă��Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮA���Y���Ƃ��c�ނ��߂̎��Ə��Ƃ��Ďg�p����{�݂��{�M�Ɋm�ۂ���Ă��邱�ƁB
2�D�\���ɌW�鎖�Ƃ̋K�͂����̂����ꂩ�ɊY�����Ă��邱�ƁB
�@ ���̌o�c���͊Ǘ��ɏ]������҈ȊO�ɖ{�M�ɋ��Z����2�l�ȏ�̏�̐E���i�@�ʕ\��1�̏㗓�̍ݗ����i�������čݗ�����҂������B�j���]�����ĉc�܂����̂ł��邱�ƁB
�A ���{���̊z���͏o���̑��z��5�S���~�ȏ�ł��邱�ƁB
�B �@���͇A�ɏ�����K�͂ł���ƔF�߂�����̂ł��邱�ƁB
3�D�\���l�����Ƃ̊Ǘ��ɏ]�����悤�Ƃ���ꍇ�́A���Ƃ̌o�c���͊Ǘ��ɂ���3�N�ȏ�̌o���i��w�@�ɂ����Čo�c���͊Ǘ��ɌW��Ȗڂ��U�������Ԃ��܂ށB�j��L���A���A���{�l���]������ꍇ�Ɏ��V�Ɠ����z�ȏ�̕�V���邱�ƁB
�O���l�����{�ŋN�Ƃ�����C�����̎��Ƃ̌o�c���͊Ǘ��ɏ]������ꍇ�C���̊����́u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�ɊY�����邱�ƂƂȂ�܂��B
�T�D���Ə��̗v���y�ю��Ƃ̌p�����ɂ���
�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�ɂ��ẮC���Ə��̗v���ɂ��ẮA�x���`���[��ƂȂǂƂ��ċ����ꂽ��Ƃɂ��ẮC�ݗ������͋K�͂����������Ƃ⏭�l���ł̎��Ɖ^�c���\�ł��邱�Ɠ�����C�Z���Ƃ��Ă��g�p���Ă���{�݂����Ə��ƒ�߂Ď��Ƃ��s���ꍇ��������܂��B�܂��C�ݗ����Ԃ̍X�V���\�����ɂ����āC���Y���Ƃ̌o�c�E�Ǘ��Ƃ����ݗ��������p�����čs�����Ƃ��ł��邩�Ƃ����ϓ_����C�Ԏ����Z�����^������߂�ꍇ�����蓾�锽�ʁC�ʏ�̊�Ɗ����̒��ł��C���ʂ̎���ɂ��Ԏ����Z�ƂȂ��Ă��Ă��C�ݗ������̌p�����Ɏx��͂Ȃ��ꍇ���z�肳��܂��B
�����Ɋւ��A����27�N�ɃK�C�h���C����������Ă��܂��B
���Ə��Ƃ�
���Ə��ɂ��Ă͎��̂悤�ɒ�`����Ă��܂��B
�i�����Ȃ���߂���{�W���Y�ƕ��ވ�ʌ�����j
�@���o�ϊ������P��̌o�c��̂̂��Ƃɂ����Ĉ��̏ꏊ���Ȃ킿������߂čs���Ă��邱�ƁB
�@�����y�уT�[�r�X�̐��Y���͒��C�l�y�ѐݔ���L���āC�p���I�ɍs���Ă��邱�ƁB
�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�ɌW�銈���ɂ��ẮC���Ƃ��p���I�ɉ^�c����邱�Ƃ����߂��邱�Ƃ���C���P�ʂ̒Z���Ԓ��݃X�y�[�X���𗘗p������C�e�Ղɏ����\�ȉ��䓙�𗘗p�����肷��ꍇ�ɂ́C��ȗ߂̗v���ɓK�����Ă���Ƃ͔F�߂��܂���B
���ݕ���
���Ə��ɂ��ẮC���ݕ�������ʓI�ł����C
�E���ݎ،_��ɂ����Ă��̎g�p�ړI�����Ɨp�C�X�܁C�����������ƖړI�ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��邱��
�E���ݎ،_��҂ɂ��Ă����Y�@�l���̖��`�Ƃ��C���Y�@�l���ɂ��g�p�ł��邱�Ƃm�ɂ��邱��
���K�v�ł��B
�������C�Z���Ƃ��Ē����Ă��镨���̈ꕔ���g�p���Ď��Ƃ��^�c�����悤�ȏꍇ�́C
�E�Z���ړI�ȊO�ł̎g�p��ݎ傪�F�߂Ă��邱�Ɓi���Ə��Ƃ��Ď؎�Ɠ��Y�@�l�̊Ԃœ]�ݎ���邱�Ƃɂ��C�ݎ傪���ӂ��Ă��邱�ƁB�j
�E�؎�����Y�@�l�����Ə��Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ�F�߂Ă��邱��
�E���Y�@�l�����Ƃ��s���ݔ�������������ƖړI��L�̕�����L���Ă��邱��
�E���Y�����ɌW������������̋��p��p�̎x���Ɋւ���挈�߂����m�ɂȂ��Ă��邱��
�E�Ŕގ��̎Љ�I�W�����f���Ă��邱��
��K�v�Ƃ��܂��B
�@�Ȃ��C�C���L���x�[�^�[�i�o�c�A�h�o�C�X�C��Ɖ^�c�ɕK�v�ȃr�W�l�X�T�[�r�X���ւ̋��n�����s���c�́E�g�D�j���x�����Ă���ꍇ�ŁC�\���l���瓖�Y���Ə��ɌW��g�p���������̒�o���������Ƃ��́C�i�Ɓj���{�f�ՐU���@�\�i�i�d�s�q�n�j�Γ������r�W�l�X�T�|�[�g�Z���^�[�i�h�a�r�b�j���̑��C���L���x�[�V�����I�t�B�X���̈ꎞ�I�ȏZ�����͎��Ə��ł����āC�N�Ǝx����ړI�Ɉꎞ�I�Ɏ��Ɨp�I�t�B�X�Ƃ��đݗ^����Ă�����̂̊m�ۂ������āC��ȗ߂ɂ���u���Ə��̊m�ہi���݁j�v�̗v���ɓK�����Ă�����̂Ƃ��Ď�舵���܂��B
����P
�l�o�c�̈��H�X���c�ނƂ��čݗ����i�ύX�\�����s�������C�������Ƃ���镨���ɌW����ݎ،_��ɂ�����g�p�ړI���u�Z���v�Ƃ���Ă������̂́C�ݎ�Ƃ̊ԂŁu��Ђ̎������v�Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ�F�߂�Ƃ����������킵�Ă���C���Ə����m�ۂ���Ă���ƔF�߂�ꂽ�B
����Q
���Y���̗A�o���y�щ��H�̔��Ƃ��c�ނƂ��čݗ����i�F��ؖ�����t�\�����s�������C�{�X����������ł������C�x�ЂƂ��ď��H��L�̕���������Ă������Ƃ���C���Ə����m�ۂ���Ă���ƔF�߂�ꂽ���́B
����R
���Ə����Z���ł���Ǝv���C���������Ƃ���C�Q�K���ăA�p�[�g�ŗX�֎C���ւɂ͎Ж���\���W�����͂Ȃ��������́B�܂��C������������@�퓙�͐ݒu����Ă��炸�C�Ƌ�̈�ʓ��퐶�����c�ޔ��i�݂̂ł��������Ƃ���C���Ə����m�ۂ���Ă���Ƃ͔F�߂��Ȃ������B
���Ƃ̌p�����ɂ���
�@���Ɗ����ɂ����Ă͗l�X�ȗv���ŐԎ����Z�ƂȂ蓾��Ƃ���C���Y���Ƃ̌p�����ɂ��ẮC����̎��Ɗ������m���ɍs���邱�Ƃ������܂�邱�Ƃ��K�v�ł��B�����ŁC�P�N�x�̌��Z���d������̂ł͂Ȃ��C�ݎ؏����܂߂đ����I�ɔ��f���邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ���C���ߓ���̌��Z�ɂ�莟�̂Ƃ����舵���܂��B
���ߊ����ɂ����ď�]��������ꍇ���͏�]�������������Ȃ��ꍇ�ɂ́C���Ƃ̌p����������ƔF�߂��܂��B
����P
�@���Y��Ƃ̒��ߊ����Z���ɂ��ƁC�����������������Ă�����̂́C�����߂Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�܂����Ђɂ��Ă͑�P���̌��Z�ł��鎖��ɂ��ӂ݁C���Y���Ƃ̌p����������ƔF�߂�ꂽ�B
����Q
�@���Y��Ƃ̒��ߊ����Z���ɂ��ƁC���㑍�����i���㍂�|���㌴���j���������Ă��邱�ƁC�������v�͐Ԏ��Ō�����������C�܂��C�������̊z�͎��{���̖�Q�{���������Ă��邱�Ƃ���C���Y���Ƃ̌p������F�߂��Ȃ������B
�o���ɂ���
�u ���{���̊z���͏o���̑��z��5�S���~�ȏ�ł��邱�ƁB�v�̗v���ɂ��ẮA�����܂ŁA���ƋK�͂̊�ł���A�\���l�{�l���A500���~�ȏ���o�����邱�Ƃ����߂Ă���킯�ł͂���܂���B�Ȃ��A���w�����N�Ƃ���ꍇ�A���̓����̌����͌������R������܂��B���i�O�����ł͏T28���Ԃ܂ł��������ł��Ȃ�����ł��B
�u��̐E���v�ɂ���
�E�A�J�n�̍ݗ��������O���l�͊Y�����܂���B�i�܂�A���{�ɋ��Z������{�l�A�i�Z�҂Ȃǂ̐g���n�ݗ������Y�����܂��j
�E�p�[�g�A�ݐЏo���A�h���A�����̌`�Ԃ͏�ΐE���ƈ����܂���B
�����o��
�u���Ƃ̊Ǘ��ɏ]�����悤�Ƃ���ꍇ�́A���Ƃ̌o�c���͊Ǘ��ɂ���3�N�ȏ�̌o���v���K�v�ł����A�����������ŁA��w�@�ɂ����Čo�c���͊Ǘ��ɌW��Ȗڂ��U�������Ԃ��܂ނƂȂ��Ă���̂ŁAMBA�ے��̊��Ԃ��܂܂�܂��B
�U�D�o�c���͊Ǘ��ȊO�̌��Ƃ͔F�߂���H
�o�c���͊Ǘ��ɏ]����������A�����Ȍo�c���͊Ǘ��ɂ����銈���̂ق��ɁA���̈�Ƃ��āA���Ɓi����̍�ƂȂǁj�ɏ]���ł��邩�Ƃ����_�ɂ��Ăł��B���̋Ɩ����]���銈���ł���ΔF�߂��܂��B�܂�A�]���銈���ł������A���i�O�����Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�������Ȃ���A����͂��Ȃ����I�ȉ^�p�ł��̂ŁA���炩���߁A�o�c�҂����Ƃ�\�肵�Ă���悤�ȏꍇ�͔F�߂��Ȃ��ƍl�����܂��B
��j
���ؗ����X�̌o�c�ҁi�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�j�ɂ����ẮA���̌o�c�̈�Ƃ��Ē����Ɩ����s�����Ƃ͖�肠��܂���B�������A�����܂ŏ]����Ɩ��łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ŁA��]�t�]�ƂȂ�Ȃ��悤�ɋC��t���܂��傤�B
�V�D���Z�@�ւ̌����J�݂��o���Ȃ��ꍇ
�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�̂��߁A��Ђ�V�ɐݗ�����ꍇ�ł����A���Z�@�ւ̌������J�݂ł��Ȃ��ꍇ�͂ǂ�����悢�̂ł��傤���B��Аݗ��̂��߂ɒZ���؍݂̋��čݗ����Ă���O���l�̏ꍇ�́A�Z���o�^���ł��܂��A���{�̋�s�ȂǂɌ������J�݂���͓̂���ł��B��Аݗ��̏o���������ނ̂ɉ�Ђ̌������K�v�ł����A��J����P�[�X�������悤�ł��B���̂悤�ȏꍇ�́A���{�l�܂��͒������ݗ����Ă���O���l���������N�l�Ƃ��āA���̕��̌����ɏo�����i�܂��͎��{���j�����݂܂��B���̌�A��Аݗ����ꂽ��A���̕��̊�����S�����������@������܂��B�Ȃ��A�V�݉�Ђ̑�\�҂ɂ��āA���{�ɏZ�����Ȃ��Ƃ��o�L�ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�i�����Q�V�N�j
�������A���{�@�l�̌o�c�҂ɏA�C���A��V�����炤�ꍇ�͒Z���؍݂ŗ�������̂́A��c�ړI�ł����Ă���@�ł���A�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i�Ă��痈�����Ȃ�������Ȃ��̂Œ��ӂ��܂��傤�B
�W�D�ݗ������i�K�ŗ�������ꍇ�̕��@
��Ђ̐ݗ��́A�@�芼�쐬�ˇA�芼�F�ˇB���{���̕����݁ˇC�ݗ��o�L�Ƃ�������ɂȂ�܂����A���̐ݗ��̂��߂̏��������邽�߂ɁA�O���l�{�l���Z���؍݂̋��ŗ�������P�[�X�͂���Ǝv���܂����A�O�q�̂Ƃ���A�Z���o�^���ł��܂��A���Z�@�ւ̌����J�݂�����̂ŁA���ɕ��@�͂Ȃ��̂ł��傤���H
���́A���̂悤�ȃP�[�X��z�肵���A�ݗ����ԂS�P���ł́u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����i���F�߂���ꍇ������̂ł��B
�u�o�c�E�Ǘ��v�̍ݗ����F��ؖ�����t�\���̒�o�����Ƃ��āA�u�@�l�̓o�L���������Ă��Ȃ��Ƃ��́A�芼���̑����Y�@�l�ɂ����ē��Y���Ƃ��J�n���悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��鏑�ނ̎ʂ��v�Ƃ������e���L�ڂ���Ă��܂��B����́A�O���l��������Г���ݗ����悤�Ƃ���Ƃ��A�ڍׂȎ��ƌv�揑��F�ؑO�̒芼�Ȃǂ��犔����Аݗ��̏������s���ӎv�����邱�Ƃ�A�ݗ����قڊm���Ɍ����܂�邱�Ƃ��m�F�ł���A�芼�F�ؑO�ł��A�ݗ����ԂS�P���́u�o�c�E�Ǘ��v�̋��������鐧�x�ł��B
�܂��A�������̒��ݎ،_��ɂ��Ă��_��O�ł������̋�̓I�ȏꏊ�A�����A�L���A�\�Z�Ȃǂ̐��������ł悢�Ƃ���Ă��܂��B�S�P���̊��Ԃ́A�Z���[���쐬�����ŒZ�̊��Ԃł��B
�o�c�Ǘ��r�U�ɂ��ݗ����Ԃ́A�u5�N�v�u3�N�v�u1�N�v�u4�J���v�u3�J���v��5��ނł����A2015�N�ɓ��ǖ@�������ɂ���āA�u�����o�c�v����u�o�c�Ǘ��v�ֈڍs����A�ݗ����Ԃɂ��Ă��A�V���Ɂu4�J���v�Ƃ����ݗ����Ԃ��lj�����܂����B���́u4�J���v�Ƃ����ݗ����Ԃ��V���ɂł������ƂŁA���{�ł̋N�Ƃ����Ղ����邽�߂ƌ����Ă��܂��B
���̗��R�́A�C�O�ɍݏZ����O���l���A���͎҂Ȃ��ɓ��{�ŋN�Ƃ��邱�Ƃ͓���A����́A��Аݗ��ɕK�v�ƂȂ��s��������邱�Ƃ��قڂł��Ȃ���������ł��B�i��Аݗ��o�L�̍ۂɁA���{����U�荞�ދ�s�������K�v�ɂȂ�܂��j
3�J���̍ݗ����Ԃł͏Z���o�^���ł����A�ݗ��J�[�h�����s����Ȃ����߁A���{�ɋ��Z���鋦�͎҂̋�s��������Ȃ���Ȃ�Ȃ������킯�ł����A���ꂪ�A�u4�J���v�̍ݗ����Ԃ��F�߂�ꂽ���Ƃɂ��A�ݗ����Ԃ�3�J�����Ȃ��Ƃł��Ȃ������Z���o�^���\�ŁA�ݗ��J�[�h������\�ƂȂ�A����ɂ���ċ�s�������e�ՂɊJ�݂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�Ƃ����悤�Ȃ��ƂȂ̂ł����A���ۂɂ́A�������܂��͂����Ȃ��悤�ł��B
���̂S�P���̍ݗ���������ꂽ�ꍇ�́A���{�ɓ���������A��Ђ̓o�L�Ȃǎc���Ă���葱�������������āA�ݗ����Ԃ̍X�V�\�����s�����ƂɂȂ�܂��B���̍X�V�̍ۂɂ́A��Ђ̓o�L�����ؖ����̒�o������K�v������܂��B�������A���Z�@�ւ̌����J�݂̉ۂɂ��ẮA�S�P���̍ݗ����Ԃ̋��̒i�K�ʼn\�ł��邩�ǂ����̊m�F���K�v�ł��B
���{�̋�s�ł́A4�����̌o�c�Ǘ��r�U��6�����̃X�^�[�g�A�b�v�r�U�Ȃǂł̑؍݂ł͎�����A�����J�݂��ł��Ȃ����Ƃ������悤�ł��B�܂��A���l�ɃI�t�B�X�����̂����ۂɂ́A����P�[�X�������悤�ł��B
�X�^�[�g�A�b�v�r�U�Ƃ́F
���t�{��o�Y�Ȃ̐��x�ɂȂ�܂����A���Ɛ헪����i�����s�A�_�ސ쌧�Ȃǁj�̈ꕔ�̒n��Ő݂����Ă���u�O���l�n�Ɛl�ގ�����i���Ɓv�ƁA�o�ώY�ƏȁA�@���Ȃɂ��u�O���l�N�Ɗ������i���ƂɊւ��鍐���v�i���m���A���s�Ȃǁj�̂ǂ��炩�̐��x�𗘗p������̂ł��B
�V�K�ŋN�Ƃ���ꍇ�݂̂̓K�p�ł��B
�ݗ����i�u�o�c�E�Ǘ��v�̎擾�Ɍ����āA�܂��N�Ƃ��u���l�́A�����̂̊Y���s������Ɏ����̑n�ƌv�揑���̐\�����ނ��o���āA�����F�肳�ꂽ��u�N�Ə��������ؖ����v��n�Ɗ����Ɋւ���m�F�ؖ�������t���܂��i�����̂ɂ���ĈقȂ�܂��j�B �����Ǘ��ǂɁA�u�N�Ə��������ؖ����v��Y�t���čݗ����i�u���芈���v�̃r�U��\�����邩�A�n�Ɗ����Ɋւ���m�F�ؖ�����Y�t���Čo�c�E�Ǘ��r�U�̐\�������܂��B ���Ȃ���A�܂�6�����Ԃ̓��芈���r�U���o�c�E�Ǘ��r�U����t���Ă���܂��B
�������A6�����̑؍ݒ��͏A�J�ł��Ȃ��i���i�O�������s�j�̂Œ��ӂ��܂��傤�B
�]���āA�����ɂ́A�C�O�ɋ��Z���Ă���O���l�́A���{�l����{�ɏZ��ł���O���l�ɋ��͎҂Ƃ��āA��Ђ̋�����\������Ƃ��ĉ�Аݗ��̂��߂̎��{���������݂�I�t�B�X�̌_��Ȃǂ̎葱������`���Ă��炤���ƂɂȂ�܂��B�葱��������������A���̕��ɂ͑�\����������C���Ă��炢�܂��B
�������A����́A���l�̌����Ɏ�����U�荞�ނ킯�ł����畁�ʂɍl���Ă����X�N������킯�ŁA������������������Ȃ��悤�ɐM�p�ł��鋤���ݗ��҂�T���Ȃ���Ȃ�܂���B
�I�t�B�X�̒��݂́A�܂��́A���͎Ҍl�Œ��_����s���āA��Аݗ���ɁA���̉�Ж��`�ɕύX���邱�ƂɂȂ�܂��B�I�t�B�X�͋��Z�p�ł͂Ȃ����Ɨp�łȂ���Ȃ�܂���B
�X�D���{�̑�w���𑲋Ƃ������w���ɂ��N�Ɗ���
���ɂ����ėD�G�ȗ��w���̎����Ɉӗ~�I�Ɏ��g��ł���Ƃ�����w���i���j�ɍݐВ�����N�Ɗ������s���Ă������w�������ƌ���p�����ċN�Ɗ������s�����Ƃ���]����ꍇ�ɁA���L�Q�i�P�j�̗v���������Ƃ�O��Ƃ��āC�ݗ����i�u���芈���v�ɂ��Œ��Q�N�Ԃ̍ݗ���F�߂��܂��B
�@���@�u���w���A�E���i�v���O�����v�̍̑��Z�Ⴕ���͎Q��Z���́u�X�[�p�[�O���[�o����w�n���x�����Ɓv�̍̑��Z�i��w�C��w�@�C�Z����w���͍������w�Z�j
�܂��C���{�̑�w���i��w�C��w�@�C�Z����w�C�������w�Z���͐�C�w�Z�̐��ے��i���m�j�j�𑲋Ƃ�����Ɉ��������O���l�N�Ɗ������i���Ɩ��͍��Ɛ헪���ʋ��O���l�n�Ɗ������i���Ƃ𗘗p���Ė{�M�ɍݗ����Ă������̂́C���ԓ��ɋN�ƂɎ���Ȃ������O���l�̕��ɂ��Ă��C���L�Q�i�Q�j�̗v���������Ƃ�O��Ƃ��āC���Y���Ɨ��p��ɐV���ȑ[�u�ւ̈ڍs��F�߁C���Y���ƂɊ�Â��ݗ��ƍ��킹�čŒ��Q�N�Ԃ̍ݗ���F�߂��܂��B
�v��
�i�P�j�@�{�M�̑�w���𑲋ƌ㒼���ɐ��x�𗘗p����ꍇ
1. �\���l���{�M�ɂ����ėD�G�ȊO���l���w���̎����Ɉӗ~�I�Ɏ��g��ł���Ƃ����u���w���A�E���i�v���O�����v�̍̑��Z�Ⴕ���͎Q��Z���́u�X�[�p�[�O���[�o����w�n���x�����Ɓv�̍̑��Z�i��w�C��w�@�C�Z����w���͍������w�Z�j�𑲋Ɩ��͏C�����Ă��邱�ƁB
�@���ΏۍZ�͈ȉ��̃����N�悩��m�F�ł��܂��B
�@�@���w���A�E���i�v���O����
�@https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1394574.htm
�@�@�X�[�p�[�O���[�o����w�n���x������
�@https://tgu.mext.go.jp/
2. �\���l����L1.�̑�w���ɍ݊w������N�Ɗ������s���Ă������ƁB
3. ��L1.�̑�w�����C�\���l���N�Ɗ������s�����Ƃɂ��Đ��E���邱�ƁB
4. ��L1.�̑�w�����C�\���l�̋N�Ɗ����ɂ��Ďx�������邱�ƁB
5. �\���l���N�Ɗ����̏���L1.�̑�w���ɕ��邱�ƁB
6. ��L1.�̑�w�����\���l�̋N�Ɗ����̌p��������ɂȂ����ꍇ���ɋA���w���E�x�����s�����ƁB
�i���j�@�v��2.�`6.�ɂ��ẮC��L1.�̑�w�������o���ꂽ���i�Q�l�l���P�j���K�v�ł��B
�i�Q�j�@�O���l�N�Ɗ������i���Ɩ��͍��Ɛ헪���ʋ��O���l�n�Ɗ������i���Ƃ̗��p��ɖ{���x�𗘗p����ꍇ
1. �\���l���{�M�̑�w���i��w�C��w�@�C�Z����w�C�������w�Z���͐�C�w�Z�̐��ے��i���m�j�j�𑲋Ɩ��͏C���������ƁB
2. �\���l����L1.�̑�w���𑲋Ɩ��͏C����C���������O���l�N�Ɗ������i���Ɩ��͍��Ɛ헪���ʋ��O���l�n�Ɗ������i���Ƃ������Ė{�M�ɍݗ����Ă����҂ł��邱�ƁB
3. �\���l���O���l�N�Ɗ������i���Ɩ��͍��Ɛ헪���ʋ��O���l�n�Ɗ������i���Ƃ����p�������̂̋N�ƂɎ��炸�C���̌�C���������{�M�ɍݗ����ċN�Ɗ������p�����悤�Ƃ���҂ł��邱�ƁB
4. �V���ȑ[�u�ւ̈ڍs�ɍۂ��āC�O���l�N�Ɗ������i���Ƃɂ�����O���l�N�Ɗ������i�c�́i�n�������c�́j���͍��Ɛ헪���ʋ��O���l�n�Ɗ������i���Ƃɂ�����W�n�������c�̂���L3.�̋N�ƂɎ���Ȃ��������R�ɂ��č����I�Ȑ������s���C���C����N�Ƃ��s�����Ƃ̊m�������������Ƃ̕]�����s�����ƁB
5. ��L4.�̒n�������c�̖��͏�L1.�̑�w�����C�\���l���N�Ɗ������s�����Ƃɂ��Đ��E���邱�ƁB
6. ��L4.�̒n�������c�̖��͏�L1.�̑�w�����C�\���l�̋N�Ɗ����ɂ��Ďx�������邱�ƁB
7. �\���l���N�Ɗ����̏���L4.�̒n�������c�̖��͏�L1.�̑�w���ɕ��邱�ƁB
8. ��L4.�̒n�������c�̖��͏�L1.�̑�w�����\���l�̋N�Ɗ����̌p��������ɂȂ����ꍇ���ɋA���w���E�x�����s�����ƁB
�i���j�@�v��3.�`4.�ɂ��ẮC��L4.�̒n�������c�̂����o���ꂽ�]�����i�Q�l�l���Q�j���K�v�ł��B
�i���j�@�v��5.�`8.�ɂ��ẮC��L4.�̒n�������c�̖��͏�L1.�̑�w�������o���ꂽ���i�Q�l�l���R�j���K�v�ł��B
�Q�l�L��
 �Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��̃r�U�擾���@
�Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��̃r�U�擾���@
�܂��͂��C�y�ɂ����k�������B
�����@AM9:00-18:00
�d�b�E���[���Ō�\��������Γy�E���E�j�����Ή��������܂��B
�@.jpg) 042-595-6071�@
042-595-6071�@