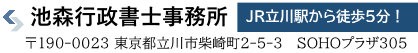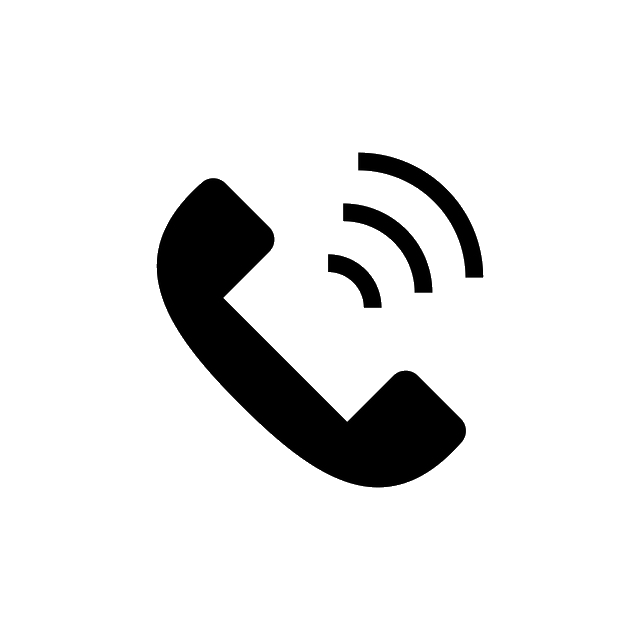�ݗ����i��Q&A
���{�ł̎d���ɕύX���Ȃ��C�������������d���ɏ]�������̂ł���C���ݗL���Ă���u�Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��v�̍ݗ����i�̂܂܂ōݗ����邱�Ƃ��\�ł����C�܂��C���{�l�ƌ������ꂽ��Ɂu���{�l�̔z��ғ��v�̍ݗ����i�֍ݗ����i�ύX���\�����s�����Ƃ��\�ł��B�Ȃ��C�u���{�l�̔z��ғ��v�ւ̍ݗ����i�ύX�����F�߂�ꂽ�ꍇ�́C�A�J�����i�E��j�ɐ������Ȃ��Ȃ�܂��B
�]�E��̊��������݂̍ݗ����i�Ɋ�Â������ƕς��Ȃ��ꍇ�́C�ݗ����ԍX�V���\�����s�����ƂɂȂ�܂��B
�]�E��̊��������݂̍ݗ����i�Ɋ�Â���������ς��ꍇ�ɂ́C�ݗ����i�ύX���\�����s�����ƂɂȂ�܁B
������̏ꍇ���C�K���ݗ������܂łɍs���Ă��������B
�u�A�J���i�ؖ����v�̌�t�\�����s�����Ƃŏؖ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�㗤��ȗ߂Œ�߂�w��v���́u��w�v�ɂ͊O���̑�w���܂܂�܂��B
�܂��C�u�����ȏ�̋���v�Ƃ́C���琧�x��C�����ɂ͑�w�ɓ�����܂��C���琅���C�Ґ����̓_�����w�Ɠ���������قǂ̓��e��L����悤�ȋ@�ւŋ�������ꍇ�Ȃǂ��Y�����܂��B
���̊Y�����ɂ��ẮC�e���̋��琧�x�C�w�Z���x�̉��ɂ����铖�Y����@�ւ̐��i�C������e�y�ѐ����܂��C�ʓI�ɔ��f����܂��B
�u���w�v�̍ݗ����i�ōݗ����Ă��钆�����ݗ��҂��]�Z�����ꍇ�C�P�S���ȓ��ɒn���o�����ݗ��Ǘ��Ǔ��ɑ��āC�]�Z�ȑO�ɍݐЂ��Ă�������@�ւɂ����闣�E�̓͏o�y�ѓ]�Z�Ȍ�ɍݐЂ��鋳��@�ւɂ�����ݐЂ̓͏o�̕K�v������܂��B
�O���l�̕����{���̊������s���T��C�A���o�C�g���̎����銈�������s���ꍇ�ɂ́C�n�������Ǘ������ɂ����Ď��i�O����������K�v������܂��B
�}�{�҂����w���̏ꍇ�C��w���y�ѐ�C�w�Z���ے��ɂ����ċ�����Ă��闯�w���̕}�{����z��ҋy�юq�������C�ݗ����i�u�Ƒ��؍݁v�ɂ��Ăъ̑Ώۂɂ͂Ȃ�܂���B
�ό��̊����́C�ݗ����i�u�Z���؍݁v�Ɋ܂܂�C���̍ݗ����i�ł͓��ǖ@�{�s�K����P�X���̂R�ɒ�߂��Ă���u�Վ��̕�V�v���ɊY�������V�݂̂��銈�����s���ꍇ�������ē������Ƃ͂ł��܂���B
�ݗ����i�̕ύX��ݗ����Ԃ̍X�V�C�ē������Ȃǂ̍ݗ��W�̐\���́C�\���l�̏Z���n���NJ�����n�������Ǘ������ŁC�\���l�{�l���o�����čs���܂��B�Ȃ��C�\���l�̖@��㗝�l�͐\���l�{�l�ɑ����Đ\�����s�����Ƃ��ł���ق��C�����@�֓��̐E���i�n���o�����ݗ��Ǘ��ǒ��̏��F���K�v�ł��B�j�C�ٌ�m��s�����m�i�n���o�����ݗ��Ǘ��ǒ��ɓ͏o���K�v�ł��B�j���͐e���Ⴕ���͓����l���i�\���l���P�U�Ζ����̏ꍇ���͎��a���̎��R�ɂ��{�l���o���ł��Ȃ��ꍇ�B�j���C�\�����ނ̒�o���̎葱���s�����Ƃ��\�ł��B
�����ē������Ƃ͍ē������̗L�����ԓ��ł���C����ł��o�������ł��܂��B����ɑ�������̍ē������͈���̏o�������s�����Ƃ��ł��鋖�ƂȂ��Ă��܂��B
�ē������̗L�����Ԃ́C�ē������̌��͔����̓�����T�N�i���ʉi�Z�҂̕��͂U�N�j���Ȃ��͈͂ŋ�����܂��B�Ⴆ�C�ݗ����������͔����̓�����T�N�ȓ��ɓ�������ꍇ�ɂ͂��̍ݗ������܂ōē��������邱�Ƃ��ł��܂��B
�ݗ����i�擾�̐\�����s���K�v������܂��B���̐\���͏o���̓�����R�O���ȓ��ɏZ���n���NJ�����n�������Ǘ������ɂ����čs���Ă��������B�Ȃ��C�o���̓�����U�O���ȓ��ɓ��{����o������ꍇ�i�ē������i�݂Ȃ��ē��������܂ށB�j���ďo�����悤�Ƃ���ꍇ�������܂��B�j�́C�ݗ����i�擾�̐\���̕K�v�͂���܂���B
�O���l�̕����{���̊������s���T��C�A���o�C�g���̎����銈�������s���ꍇ�ɂ́C���i�O����������K�v������܂��B
���ǖ@�ɂ�����g���ۏؐl�Ƃ́C�O���l���䂪���ɂ����Ĉ���I�ɁC���C�p���I�ɏ����̓����ړI��B���ł���悤�ɁC�K�v�ɉ����ē��Y�O���l�̌o�ϓI�ۏ؋y�і@�߂̏��瓙�̐����w�����s���|��@����b�ɖ���l�������܂��B �g���ۏ؏��̐��i�ɂ��āC�@����b�ɖ���ۏ؎����ɂ��Đg���ۏؐl�ɑ���@�I�ȋ����͂͂Ȃ��C�ۏ؎����𗚍s���Ȃ��ꍇ�ł����ǂ���̖̗��s���w������ɂƂǂ܂�܂����C���̏ꍇ�C�g���ۏؐl�Ƃ��ď\���ȐӔC���ʂ�����Ȃ��Ƃ��āC����ȍ~�̓����E�ݗ��\���ɂ����Đg���ۏؐl�Ƃ��Ă̓K�i���������Ƃ����ȂǎЉ�I�M�p���������Ƃ���C����Γ��`�I�ӔC���ۂ����̂ł���Ƃ����܂��B
���ǖ@�ł͉i�Z���������v���Ƃ��āu�f�s���P�ǂł��邱�Ɓv�C�u�Ɨ��̐��v���c�ނɑ���鎑�Y���͋Z�\��L���邱�Ɓv�̂Q�_���f���C���̏�Łu�@����b�����̎҂̉i�Z�����{���̗��v�ɍ�����ƔF�߂��Ƃ��Ɍ���C����������邱�Ƃ��ł���B�v�ƋK�肵�Ă��܂��B
�܂��C���ǖ@�ɋK�肷���L�Q�̗v���ɂ��Đ������܂��B�Ȃ��C�����̗v���͐\���l���u���{�l�C�i�Z�����Ă���Җ��͓��ʉi�Z�҂̔z��Җ��͎q�ł���ꍇ�ɂ����Ă͓K�����邱�Ƃ�v���Ȃ��B�v�ƋK�肳��Ă��܂��B����́C�{�M�ɐ�����Ղ�L���邱�Ƃ����炩�Ȃ����̊O���l�ɂ��Ă͂��̗v�����ɘa���Ƒ��P�ʂł̍ݗ��̈��艻��}�邱�Ƃ������Ƃ̍l���ɂ����̂ł��B
�u�f�s���P�ǂł��邱�Ɓv�Ƃ́C�䂪���̖@�߂Ɉᔽ���āC�����C�������͔����ɏ�����ꂽ���Ƃ��Ȃ����ƁC���͏��N�@�ɂ��ی쏈�����łȂ����Ƃ̂ق��C���퐶���ɂ����Ă��Z���Ƃ��ĎЉ�I�ɔ���邱�Ƃ̂Ȃ��������c��ł��邱�Ƃ������܂��B
�u�Ɨ��̐��v���c�ނɑ���鎑�Y���͋Z�\��L���邱�Ɓv�Ƃ́C���퐶���ɂ����Č����̕��S�ƂȂ��Ă��炸�C���C���̗L���鎑�Y���͋Z�\������݂ď����ɂ����Ĉ��肵�������������܂�邱�Ƃ������܂��B����́C�\���l���g�ɔ�����Ă��Ȃ��Ƃ��C�z��ғ��ƂƂ��ɍ\�����鐢�ђP�ʂŌ����ꍇ�Ɉ��肵���������p���ł���ƔF�߂���ꍇ�͂��̗v�������Ă�����̂Ƃ���܂��B
�u�@����b�����̎҂̉i�Z�����{���̗��v�ɍ�����ƔF�߂��Ƃ��Ɍ���C����������邱�Ƃ��ł���B�v�Ƃ́C���̎҂ɉi�Z�������邱�Ƃ��C���{�̎Љ�C�o�ςɂƂ��ėL�v�ł���ƔF�߂�����̂łȂ��Ă͂Ȃ�܂���B���̔��f�́C���y�̏����C�l���̓��������{�Љ�̊O���l�����\�́C�o�����Ǘ������܂����O�̏�����̑������鎖������Ă��čs������̂ŁC�i�Z�̋���^����ۂ��ɂ��ẮC�@����b�̍L�͂ȍٗʂ��F�߂��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@��̓I�ȗ�Ƃ��ẮC�����Ԃɂ킽��䂪���Љ�̍\�����Ƃ��ċ��Z���Ă���ƔF�߂��邱�ƁC�[�ŋ`�������I�`���𗚍s���Ă��邱�Ƃ��܂߁C�@�߂����炵�Ă��邱�Ƃ��F�߂��邱�ƁC�����̕��S�ƂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ��F�߂���Ȃǂ��������܂��B
�ݗ����i�����������̂́C�傫�������Ď��̂R��ނ̏ꍇ������܂��B
�@ �U�肻�̑��s���Ȏ�i�ɂ�苖�����ꍇ
�㗤�̐\����ݗ����Ԃ̍X�V�̐\���̍ۂɁC�U�ϑ����ꂽ�����⎑�����o������C�\�����ɋU��̋L�ڂ�������C�U��̐\���Ă����邱�Ɠ��ɂ���āC�������ꍇ��������܂��B
�A �{���̍ݗ����i�Ɋ�Â��������p�����Ĉ����ԍs���Ă��Ȃ��ꍇ
���̏ꍇ��������܂��B�������C�������s��Ȃ����Ƃɂ��Đ����ȗ��R������ꍇ�́C�ݗ����i������̑ΏۂƂ͂Ȃ�܂���B I.���ǖ@�ʕ\���̍ݗ����i�i�Z�p�C�Z�\�C�l���m���E���ۋƖ��C���w�C�Ƒ��؍ݓ��j�������čݗ����Ă���O���l���C���̍ݗ����i�Ɋ�Â��{���̊������p�����ĂR�����ȏ�s���Ă��Ȃ��ꍇ
II.�u���{�l�̔z��ғ��v�i���{�l�̎q�y�ѓ��ʗ{�q�������B�j���́u�i�Z�҂̔z��ғ��v�i�i�Z�ғ��̎q�Ƃ��Ė{�M�ŏo�������҂������B�j�̍ݗ����i�������čݗ����Ă���O���l���C���̔z��҂Ƃ��Ă̊������p�����ĂU�����ȏ�s���Ă��Ȃ��ꍇ
�B �������ݗ��҂��Z���n�̓͏o���s��Ȃ��ꍇ���͋��U�̓͏o�������ꍇ
���̏ꍇ��������܂��B�������C�T�y�чU�ɂ��āC�͏o�����Ȃ����Ƃɂ��Đ����ȗ��R������ꍇ�́C�ݗ����i������̑ΏۂƂ͂Ȃ�܂���B I.�㗤�̋���ݗ����i�̕ύX�����ɂ��V���ɒ������ݗ��҂ƂȂ����҂��C�X�O���ȓ��ɖ@����b�ɑ��Z���n�̓͏o�����Ȃ��ꍇ
II.�������ݗ��҂��C�@����b�ɓ͂��o���Z���n����ދ�����������X�O���ȓ��ɁC�@����b�ɐV�����Z���n�̓͏o�����Ȃ��ꍇ
III.�������ݗ��҂��C�@����b�ɋ��U�̏Z���n��͂��o���ꍇ
�ݗ����i���������ꂽ��̎戵���͓��ނ���܂��B
�s����i���̍s�g�ɂ��Ĉ������������ꍇ�i�㗤���ێ��R�ɊY�����Ă��邱�Ƃ��U�����ꍇ����{�ł̊������e���U�����ꍇ�j�ɂ́C�ݗ����i���������ꂽ��C�����ɑދ������̎葱�������܂��B
����C�s����i���̍s�g�ɂ��Ĉ������������Ȃ��ꍇ�i�\���l���o�����U�����ꍇ��\���l�ȊO�̎҂������ƈقȂ镶�������o�����ꍇ�j��ݗ����i�Ɋ�Â��{���̊������p�����Ĉ����ԍs���Ă��Ȃ��ꍇ��C�������ݗ��҂��Z���n�̓͏o���s��Ȃ��ꍇ���͋��U�̓͏o�������ꍇ�ɂ́C�ݗ����i�����������ۂɁC�O�\�����Ȃ��͈͓��ŏo�����邽�߂ɕK�v�ȏ������ԁi�o���P�\���ԁj���w�肳��C�����ԓ��Ɏ���I�ɏo�����邱�ƂɂȂ�܂��B
�ݗ����i�̎�����̍ۂɎw�肳�ꂽ���ԓ��ɏo�����邱�Ƃ́C�ݗ����ԓ��ɏo������ꍇ�Ɠ��l�Ɏ�舵���܂��B
���ǖ@�ʕ\���̍ݗ����i�i�Z�p�C�Z�\�C���w���j�������ē��{�ɍݗ����Ă���O���l���C���̍ݗ����i�ɌW�銈�����p�����ĂR�����ȏ�s���Ă��Ȃ��ꍇ�ł��C���̊������s��Ȃ��ōݗ����Ă��邱�Ƃɂ��āu�����ȗ��R�v������Ƃ��́C�ݗ����i�̎�����̑ΏۂƂ͂Ȃ�܂���B
�u�����ȗ��R�v�̗L���ɂ��ẮC�ʋ�̓I�ɔ��f���邱�ƂƂȂ�܂����C�Ⴆ�C���̂悤�ȃP�[�X�ɂ��ẮC�u�����ȗ��R�v��������̂Ƃ��čݗ����i�̎�����̑ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��ꍇ������܂��B
�@ �ғ����ސE��C�ďA�E���T�����߂ɉ�ЖK�������ȂNj�̓I�ȏA�E�������s���Ă���ƔF�߂���ꍇ
�A �ݐЂ��Ă�������@�ւ��Z������C���̋���@�ւɓ��w���邽�߂ɕK�v�Ȏ葱��i�߂Ă���ꍇ
�B �a�C���Â̂��ߒ����Ԃ̓��@���K�v�ł�ނ�����@�ւ��x�w���Ă���҂��C�މ@��͕��w����ӎv��L���Ă���ꍇ
�C ��C�w�Z�𑲋Ƃ������w�����{�M�̑�w�ւ̓��w�����肵�Ă���ꍇ
�u���{�l�̔z��ғ��v�i���{�l�̎q�y�ѓ��ʗ{�q�������B�j���́u�i�Z�҂̔z��ғ��v�i�i�Z�ғ��̎q�Ƃ��Ė{�M�ŏo�������҂������B�j���C���̔z��҂Ƃ��Ă̊������p�����ĂU�����ȏ�s���Ă��Ȃ��ꍇ�ł��C���̊������s��Ȃ��ōݗ����Ă��邱�Ƃɂ��āu�����ȗ��R�v������Ƃ��́C�ݗ����i�̎�����̑ΏۂƂ͂Ȃ�܂���B
�u�����ȗ��R�v�̗L���ɂ��ẮC�ʋ�̓I�ɔ��f���邱�ƂƂȂ�܂����C�Ⴆ�C���̂悤�ȃP�[�X�ɂ��ẮC�u�����ȗ��R�v��������̂Ƃ��čݗ����i�̎�����̑ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��ꍇ������܂��B
�@ �z��҂���̖\�́i������c�u�i�h���X�e�B�b�N�E�o�C�I�����X�j�j�𗝗R�Ƃ��āC�ꎞ�I�ɔ��͕ی��K�v�Ƃ��Ă���ꍇ
�A �q���̗{�瓙��ނȂ�����̂��߂ɔz��҂ƕʋ����Đ������Ă��邪���v����ɂ��Ă���ꍇ
�B �{���̐e���̏��a���̗��R�ɂ��C�ē������i�݂Ȃ��ē��������܂ށB�j�ɂ�钷���Ԃ̏o�������Ă���ꍇ
�C �������▔�͗����i�ג��̏ꍇ
�㗤�̋��Ⴕ���͍ݗ����i�̕ύX�����ɂ��V���ɒ������ݗ��҂ƂȂ����҂��C���Y�����Ă���X�O���ȓ��ɖ@����b�ɑ��Z���n�̓͏o�����Ȃ��ꍇ���͒������ݗ��҂��C�@����b�ɓ͂��o���Z���n����ދ�����������X�O���ȓ��ɁC�@����b�ɐV�����Z���n�̓͏o�����Ȃ��ꍇ�ł��C�Z���n�̓͏o���s��Ȃ����Ƃɂ��āu�����ȗ��R�v������Ƃ��́C�ݗ����i�̎�����̑ΏۂƂ͂Ȃ�܂���B
�u�����ȗ��R�v�̗L���ɂ��ẮC�ʋ�̓I�ɔ��f���邱�ƂƂȂ�܂����C�Ⴆ�C���̂悤�ȃP�[�X�ɂ��ẮC�u�����ȗ��R�v��������̂Ƃ��čݗ����i�̎�����̑ΏۂƂ͂Ȃ�Ȃ��ꍇ������܂��B
�@ �߂Ă�����Ђ̋}�ȓ|�Y�₢����h���蓙�ɂ��Z���������C�o�ϓI�����ɂ���ĐV���ȏZ���n���߂Ă��Ȃ��ꍇ
�A �z��҂���̖\�́i������c�u�i�h���X�e�B�b�N�E�o�C�I�����X�j�j�𗝗R�Ƃ��Ĕ��͕ی��K�v�Ƃ��Ă���ꍇ
�B �a�C���Â̂��߈�Ë@�ւɓ��@���Ă��铙�C��Ï�̂�ނȂ�����F�߂��C�{�l�ɑ����ē͏o���s���ׂ��҂����Ȃ��ꍇ
�C �]����}�ȏo���ɂ��ē����o�������ꍇ���C�ē������i�݂Ȃ��ē��������܂ށB�j�ɂ��o�����ł���ꍇ
�D �p�ɂȏo�����J��Ԃ��ĂP����̖{�M�؍݊��Ԃ��Z�����̓��C�ݗ������̐�����Z���n�̐ݒ�����Ă��Ȃ��ꍇ
�Q�l�L��
 �Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��̃r�U�擾���@
�Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��̃r�U�擾���@
�܂��͂��C�y�ɂ����k�������B
�����@AM9:00-18:00
�d�b�E���[���Ō�\��������Γy�E���E�j�����Ή��������܂��B
�@.jpg) 042-595-6071�@
042-595-6071�@